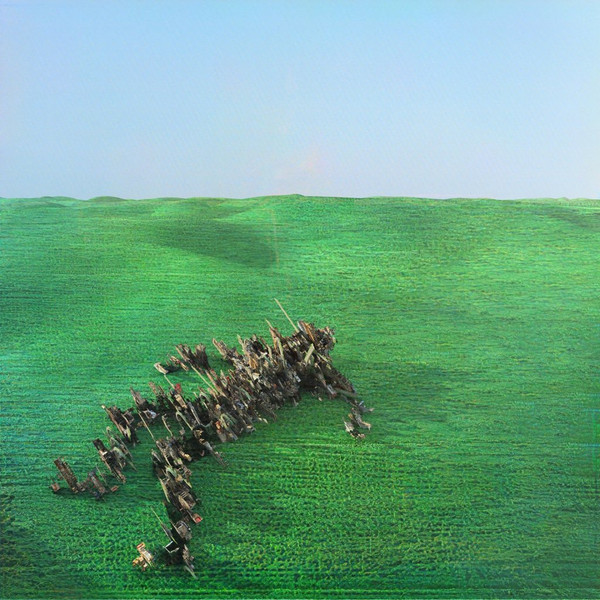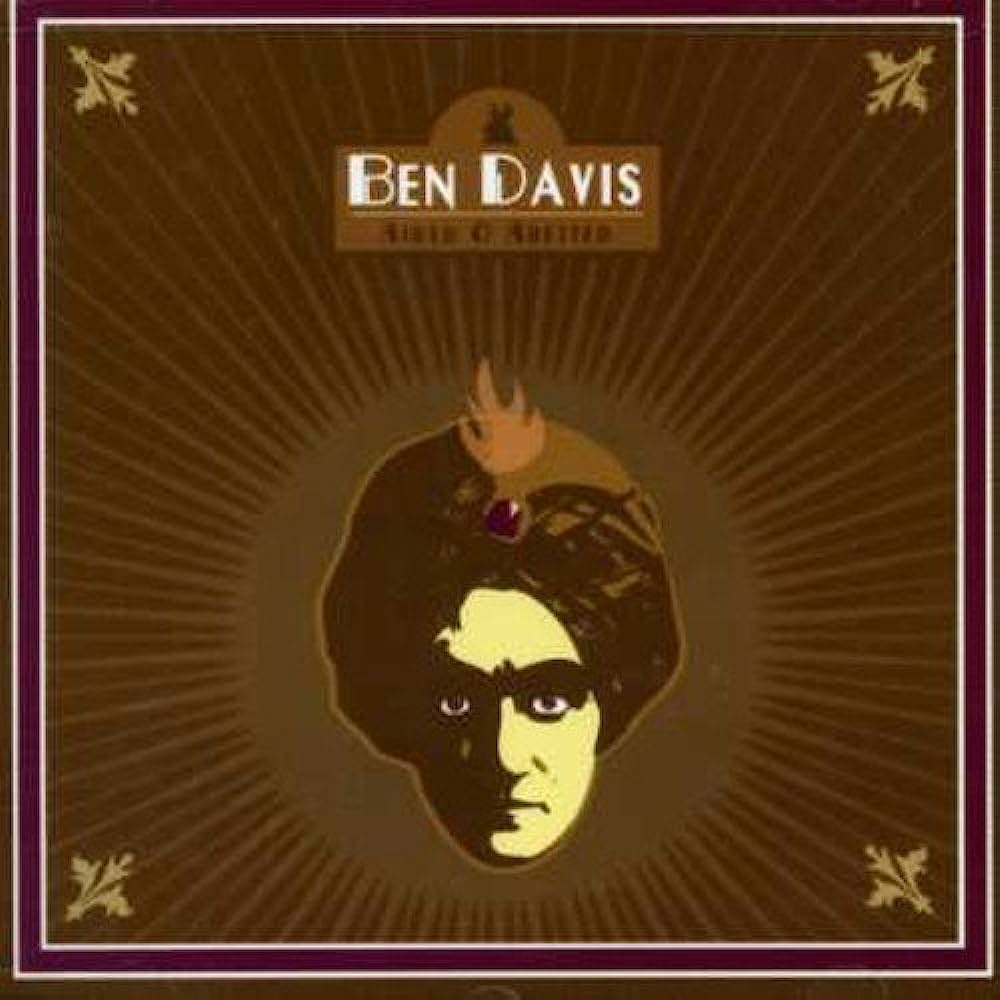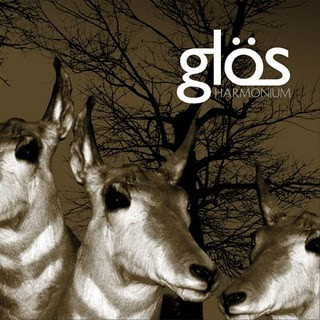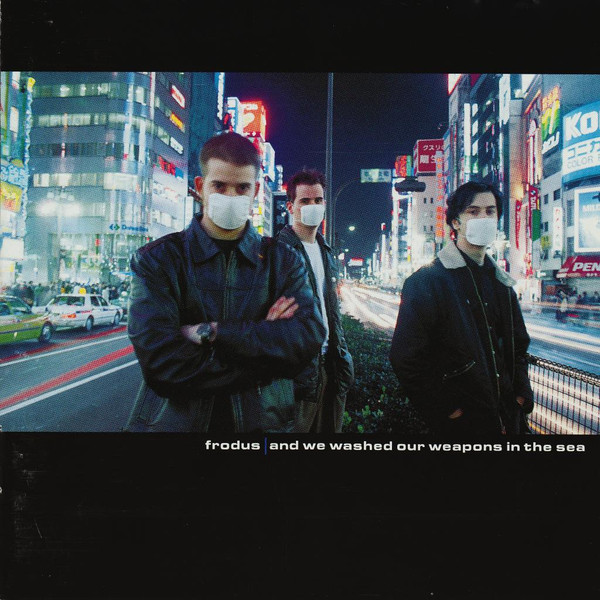上半期にリリースされた新譜でよく聞いてたものを並べました。
People In The Box、FACS、Shame、Model/Actriz、Cwondoについてはこちら
他deathcrash、Squid、butohes、SPOILMANについては単品記事にて
上記以外のアルバムについて触れていきます。
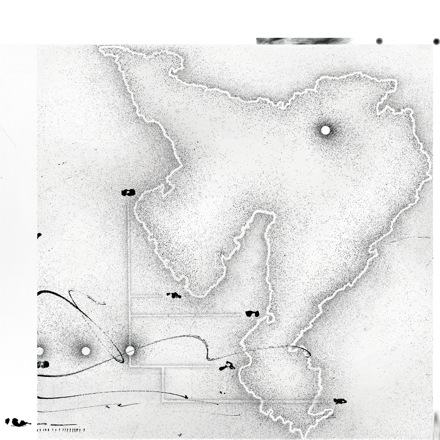
5kai。昨年末にライブを見て衝撃を受けそのまま新譜をリリース。上半期前半はずっとこのアルバムを聞いてました。元々最小限、線の細い鉄をひたすら打ちつけるような強烈なアンサンブルはスロウコアと呼ぶにはマッシブすぎる冷たいポストハードコアで、今作はそこからまた逸脱した、アコースティックギターを導入し生々しさが増し歌ものとしての要素も強めた「棚」とか、温かみすらある「ロウソク」とか、バンドの冷たさと硬さを殺さぬまま両立できるんだ?という驚きの曲達に打ちのめされた。そして一番やばいのが「祝詞」という曲、Pop Groupを想起するフリーキーなサウンドでアコギをグリッチで歪めた人力IDMみたいな様相すら見せる、ハードコアサイドのフォークトロニカみたいな感じで、自分の音楽趣味だと耳馴染みありすぎるながらも聞いたことない組み合わせでこれは本当に衝撃でした。
Cruyff - lovefullstudentnerdthings

昨年リリースされたシングルがあまりにも素晴らしく当事の上半期(上半期+7月に聞いた新譜まとめ - 朱莉TeenageRiot)でも触れたCruyff、あの時の印象をそのままアップデートしたような爆音オルタナという言葉がぴったりのフルアルバム。轟音ヘヴィシューゲイズからグランジからポストハードコアまで全突っ込み、不穏なノイズロック然としながらも最後は爽快に全部振り切って走り出してしまう「lovefullstudentnerdthings」は夏にぴったりで泣けてしまう。ポエトリーでもなければ歌ものという程でもない、しかしある程度メロディーの形はしっかり残したぼそぼそと不安定なボーカルの存在感にもすごく惹かれる。「summercut」はスマパンのサイアミーズ期なイントロからHum直系のへヴィシューゲへ。Hum自体がスマパンフォロワーという経緯を考えると中々に熱いし、ギターロックの系譜にしっかりと乗ったナンバガもNirvanaもFugaziもSmashing Pumkinsが好きな人も全員是非という感じです。

とにかく「International Lily White」があまりにもすごすぎて圧巻です。同タイトルの架空の映画のサントラを聞いているような、作品の記憶を脳内に植えつけられてしまったかと錯覚してしまう壮大な曲群。AとBに分割されていてSpotifyだと全4曲24分、しかしこれもただアルバムの一部でしかなくこの体験を終えた後始まる「Brocade」がストレートに真っ直ぐ突き刺さってくるギターロックの名曲でこの構成にも泣ける。今年ベストトラックかもしれません。BorisのNew Albumで言うLoopriderのポジというか、カオスであること自体が一つの一貫性足りえるという聞いたときの印象という意味でもNew Albumを連想したのかも。すごくバラエティに富んでいてworld's end girlfriendにBorisや芸能山城組、シューゲイズやポストロックまで一括りにしたオルタナ、ブレイクコアにフューチャーベースまでめまぐるしく変化する巨大な轟音世界でディーパーズのYukari Telepathも思い出す。今年はツイッターでp rosaが話題でしたが確実に同じ層に刺さる作品だと思います。

ここ数年bandcampスロウコアタグの常連とも言えるバンドで今回Run For Coverから。2018年リリースのSckrpnchというMelaina Kolとのスプリットでは夢心地な幻想世界へと旅立てる超叙情的ドリームポップが何割か入ったスロウコアで超好きだったのですが、今作はもうスロウコアでは無いけど、今までそれをやってきた土壌から出てきたことが確かにわかるエモ寄りのインディーロック。単純な静→動のコントラストだけでは描き切れなそうなどっちともとれる感じをふらふら浮遊しながらグッドメロディを乗せてくる。deathcrashがスロウコア+エモでslow moなんて単語をインタビューで使ってましたがwaveformこそslow moのイメージですね。

Exploding In Soundより同レーベルではお馴染みPileの新譜。Pileを聞くたびにこれはポストハードコア?エモ?グランジ?咀嚼され切ったバンドの音は掴みどころがなくただ自分には普段からずっと親しみのある音楽であることは間違いなくわかる、そんなPileがリリースした前作Songs Known Together, Aloneは路線変更していて電子音の海に浮かんでぷかぷかする宇宙遊泳オルタナとも言える作品でした。正直しっくりきてなかったけど、そこから2年足らず、前作と比べれば初期路線・・・とにかく好きな音が最高にかっこいい音でビシバシ鳴りまくっていて、あまりの愚直さに乾いた笑いが出た。ストレートにやられました。ハードなベースラインを軸にアンサンブルを解体してくようなフレーズの妙は安定してるのか不安定なのかわからん、統制された不協和音による崩れたヘヴィさが猛烈に刺さる。
Washer - Improved Means To Deteriorated Ends

こちらもExploding In Soundからでレーベル初期からいる古株ですがフルアルバムとしては6年ぶり。しかしいつ聞いてもWasherは本当にただひたすらメロディが良く、ジャンルとしてはエモのフィーリングありつつエモの型には嵌らない、力の抜けたジャンクなインディーロックの質感があって今回もいつも通り。ちょっとNeutral Milk Hotelも思い出しますね。
Horse Jumper of Love - Heartbreak Rules

こちらもRun For CoverからHorse Jumper of Love一年ぶりの新譜。初期のノイジーさはどんどん薄まり彼らの純粋な中身がさらけ出てきたかのような、音数を減らしソフトでアコースティックな雰囲気も出しながらもそれでも痛みを感じさせてくる繊細なインディーロック。ほんのりスロウコアフレーバーも乗っかっててとても暖かい。今まで以上に崩れた曲もあって初期のJoan of Arcを思い出したりもした。

90年代Touch and GoやSouthernの影響を受けて出てきたかのようなポストハードコア以降の硬質な音色とアンサンブル、そこにインディーロックの親しみやすさがブレンドされた現代のNeutrinoとも言える熱いバンド。めっちゃいい。本当に2023年?と思ってしまう程の2000年前後くらいのアルビニ録音のスロウコア寄りポストハードコアみたいな、解散直前のAtivinとかBedheadみたいな雰囲気もある。

Empty Classroomの坂口氏によるソロ。バンドでもおなじみの名曲「第12話」も収録されていて何度聞いても名曲で震える。開幕の「電子の砂漠」のイントロの冷たいギターやどこかくたびれ雰囲気がひんやりと心地よく、諦念感漂う言葉一つ一つにすごく居心地の良さを感じる中で、諦めてはいても言葉を吐き出さずにはいられなかったような生々しさが伝わってかなりぐっときてしまった。「シャフト」も近い温度感がありこちらも名曲。全体的に00年代ギターロックっぽいというか、GRAPEVINEでのイデア~deracine辺りのアルバム曲とか、pillowsのペナルティーライフ辺りを思い出しますね。最後のSTAGEはイントロから全て破壊してくような重厚なギターの爆音アンセムで感情全放出したような圧が凄まじく、しかも綺麗に終わらず轟音ぶつ切りでアルバムが終わってしまうところ含めてやりきれなさを感じてこちらもかなりぐっとくる。リピートにしているとこのあとまた戻ってきた電子の砂漠での、STAGEとは対照的な平熱感が、初聴時とは別のベクトルで聞こえてくるのも良い。レヴュースタァライトのファンの方はとくにオススメです。

4曲全部やばすぎるEP。「ドライブ」は全パート各々独立したリズムが交錯してもうジャズファンクみたいになってるし、「メビウス」はアンサンブル以前に音色の選択とか重ね方そのものがグルーヴに直結してて本当にすごすぎます。「チョコレート」は可愛げがあるのに気が狂ったギターが飛び回り、極端にパン振りされた両耳を交互に行き来するもう一本のギターもキーボードみたいな音色の質感が癖になる。摩訶不思議なバンドサウンドのマジックがこれでもかというくらい詰め込まれてて、全部違う方向から殴りかかってくるというか、一曲一曲次々と宝箱を開けているような気持ちになる。

突如リリースされたEP。最初の「待ち時間」からして電子音のシーケンスを軸としたミニマルなナンバー、それこそworkshopのロープ(medication ver.)みたいな、このグルーヴをメインとしながら展開していく「家の中」「ただ立ってる」とどれもこれも最近のライブを連想する。前アルバムでの乾いた質感と比べるとは今作もう少し分離が良く、それぞれの楽器の音や隙間の埋め方がはっきりと分かる音で録音されていて、そういった意味でも彼らのライブでのアプローチがここまで音源に反映されてるのとても珍しいと思います。最近の見えないルールの前振りで流れる電子音のループとかまさに一曲目っぽいですね。かと言ってライブでの無機的な反復から生演奏による有機的なグルーヴへと自然に移行してくような大きな展開はこちらにはなく、うまいことバンドにおける熱量のピーク直前にあたる部分を抽出して均等にコンパクトにまとめたすごく面白い作品だと思う。ライブや音源でもリアレンジが多いバンドですがこういう新作を届けてくれること自体嬉しいというか、醍醐味ですね。今作めちゃくちゃ70sのクラウトロックの色が強くて「長い間」はミヒャエル・ローターすぎる上に歌メロはもろCANのOh Yeahのオマージュだし、ここまで元ネタというかリファレンスを露出させてるのも珍しくてニヤリとしました。

君は放課後インソムニアのEDで流れた曲がイントロからコーラスがかった幽玄なギターの音色とどことなくThe Police風にも聞こえてリズム隊にもポストパンク/ニューウェーブを仄かに感じ、そこに日本語の歌ものとしてとてもやわらかいSSWっぽさもあるボーカルが乗ったときの折衷具合があまりにもよすぎてクレジットを見たらHomecomings・・・まるで気付けず、というか前作までのイメージからだとかなり驚きました。今までインタビュー等でリファレンスとして挙げてるバンドや比較されるジャンル、全部好きなのにも関わらず本人達のアルバムにあんましっくりきてなかったというのが正直なところで、日本語になってからも、ちょっとオルタナとかニューウェーブとかのラインではなくユーミンっぽいなと思って聞いてて歌が先行するイメージがついちゃってバンドとしてあまり聞けてなく、リズと青い鳥とか好きだったけど主題歌はしっくり来ず・・・て感じでしたが今作は間違いなく大好きと言えます。オルタナ寄りというか、「Shadow Boxer」「euphoria/ユーフォリア」はシューゲやシューゲ前夜のギターポップとかの空気を咀嚼しながら空間に寄せてドリームポップになるわけでもない、轟音すぎずでもニュアンスは引用、みたいな、ボーカルも演奏に溶け合わせるわけでもなくあくまでしっかり分離して乗っかってるのは昔ながら日本のギターロックバンドの手法として系譜があると思うし、挿入歌の「US/アス」も同系列で疾走感があって好きでした。てか放課後インソムニアめちゃくちゃ良かったよ。主題歌はaikoだし・・・

めっちゃ良かったです。「美しい鰭」も「手毬」も初期スピッツからずっと地続きなネオアコとかギターポップみたいなそういう瑞々しさがちょっとだけ年季入った雰囲気で余裕持って、かと言って手癖っぽさもなくて、とにかく先行公開された美しい鰭での透明感のあるギターのトーンからして再生数秒で心を鷲掴みにされた。流れ星とか愛の言葉とか、このバンドの持つイントロの魔力は本当に凄まじくて、再生して一発目のホーンの音がそのまま続くかと思ったらその一音のみ、フレーズの続きのメロディーをギターが引き継いでく初手インパクトとの差し引きが天才的だと思います。手毬、イントロのこの雰囲気自体が懐かしくて少し泣きそうになった上にめちゃくちゃ歌詞が良い。「手に入るはずだった未来より/素朴な今にありついた」はやばいですね。手毬って言葉の響きにかわいらしさと、今は戻ってこないかつての楽しかった思い出とか郷愁とか儚い美しさが同居している。あと「オバケのロックバンド」も好きで、イントロいきなりAC/DCみたいな土臭いハードロッキンなリフでにんまりしているとボーカルはメンバー全員担当という驚きが二度ある。
Yo La Tengo - This Stupid World

前作「There's A Riot Going On」はよく聞いてたのですが、漂っている音をそのまま掴み取って形にするのではなく素材として空間に浸らせ音色そのものと同化するみたいな、もうバンドとしての肉感を楽しむのではなく、音響全振りして幽体化したスタイルが今のYo La Tengoなのかなぁと勝手に判断していた自分にぶち込まれた極上のオルタナ/USインディー風味でギターロック好きにも刺さる名盤。そもそも彼らのフェイバリットとしてElectr-O-PuraやPainfulをベストにあげてしまう自分としてはもう、何も言うことがない。バンドのお決まりとも言うべきこのベースラインだったりギターのトーンだったりつかみどころがないようで形がしっかりした、温かみのあるノイジーでまるで毛布のようなアンサンブルの音の膜自体がそのままYo La Tengoの形状をしていて、どことなくオールディーズの雰囲気も同化してるのもすごく懐かしく、所謂USインディーって呼ばれてた90年代のバンド達と比べるとYo La Tengoはこの部分で乖離があったと思います。カバー集のFakebookがそれを象徴してたというか、その感じも今作強くてすごく良かった。

最高。Duster直系にBluetile Loungeも混じった、90年台スロウコアのオリジネイター達のおいしいとこ全部詰め込んだようなアルバム。毛布にくるまって一人でただ呆然と浸りたくなるような孤独と温かみとを同時に感じてしまう、これがまた長尺じゃなくて意外とさらっと聴けるサイズに落ち着いているのも意外です。スロウコアと言えばコップに一滴ずつ水を垂らしていくようなイメージがあるんですがCusperは繰り返すのではなく展開を増やし、その上コンパクトにまとめてしまう。

リリース前より話題になってたbar italiaの新譜で、馴染み深いどこかチープでミニマルでスカスカなバンドアンサンブルは完全に70sのポストパンクバンドの雰囲気で、Joy DivisionとかRaincortsとか、しかしそこに乗るのはまるでUSインディーのようなグッドメロディ。PavementとかHeliumのノリでも聞けてしまえる、好きな要素全部詰めこんで着飾ることなく正面からリバイバルをやってて笑顔になってしまう。これがマタドールからリリースされてるのも納得しかないです。

こちらも話題作で今までで一番すんなり聞けました。Jay Somくらいのユルいインディーポップなのに低音がえぐいくらい効いてる。Conan Mokasinっぽさもあってこういうサイケでチルなインディーロックは数年前まではいくらでも聞いてたような気がするけど今改めて聞くと懐かしくなりました。

前作はめっちゃフリーキーで比較対象がkikagaku moyouくらいまできてたイメージでしたが、今作ぎゅっと収縮したサイケなインディーポップくらいの趣で良い。King Krule新譜とも近くてAORっぽいメロウさもかなりある。あとジャケが最高ですね。
Yves Tumor - Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)

話題作。前作とかも聞いたことなくて先入観無しで聞いたらNew Orderみたいなニューウェーブが流れたり「Meteora Bluce」辺りはラウド&クワイエットな重厚なギター中心のロックで普通にART-SCHOOLみたいな感じで聞けて、ソウルフィーリングもミックスされてるしどことなくゴスっぽいダークな雰囲気もあり・・・と、そのハイブリッドさに圧倒され新しさと懐かしさが同居してすんなり聞けてしまい一瞬でファンになった。自分でも気付いてなかった欲しかったものが箱を開けたらいっぱいあったみたいな、意外とこういうアルバム一番聞きたかったかもしれないですね。
Jonah Yano - Portrait Of A Dog

完全初聴ですが良すぎてびっくりして、Sea and Cakeとかあの辺のサム・プレコップとかのジャジーなポストロックとも通じ合えそうな、しかしその辺が持ってたエクスペリメンタルな要素を抑えて純粋にジャズとロックの繋がりを強固にして練り上げて更にインディーフォーク的な素朴な歌ものフィーリングを乗せた感じで。「always」ではゆるく流してたくなるソフトな序盤から、ボーカルが無くなり長いアウトロとも言える後半のインストパートはアグレッシブにセッションのギアを上げて行く様は夢中になってしまう。肩の力抜いてのんびり聞き流せそうなラフな空気もありながら、純粋にバンドのアンサンブルの魔力でどんどん聞き入って耳を離せなくなってしまうようなところも両立した本当にすごいアルバムだと思います。
Queens of the Stone Age - In Times New Roman...

前作と同じくマタドールから。僕はとにかく数年前に出たVillansが好きでかなり聞いてたのでそのまま正面からアップデートしたような今作がハマらないわけなく、今作もあまりストーナー、メタル、グランジと言った言葉から連想するようなヘヴィなギターサウンドはそこには無い。純粋に無骨にバンドのグルーヴを露出させていくような一切の装飾を外しその上でボトムを太くしていったような、素材を見せるようなギターの音色で、決まったリフを繰り返すというよりはリズム隊と一体になるような、まるでQueens of the Stone Ageという一つの生命体の手足のように連動して動くドラムとベースとの絡みが圧倒的にかっこいい。純粋に「ロックバンドの一アルバム」という難しいこと抜きにして聞いたら今年一番のアルバムだったかもしれません。あと音が良すぎる。Spotifyの音質でもわかるくらいドラムに臨場感あって一瞬で引き込まれます。それもあってリズム隊の動きに耳を惹かれる。

ライブ音源ですが最高の曲達が最高の録音で保存されていてこれを聞いていると子供の頃どうしてロックが好きだったか、一番最初の原点を記憶の底から掬い取ってくるような、どうして今でもギターロックを聴きそこに何を期待しているのか今一度思い出させてくれたアルバム。音はかなり荒々しいですが、純粋に曲が良くてしかもギターリフはド派手なのでこの音がめちゃくちゃ映える。ジャケもかっこよすぎる。ちなみに最初の「サウスポー」は上記の坂口達也氏のSTAGEがサウンドクラウドで公開されたとき、それに触発されてできた曲らしいです。

2ndEPで前作と大分イメージが変わってて、轟音すぎないザラついた微シューゲイズであくまで隙間を残して疾走してる感じが少しギターポップみもあって、風通しのよさと歌との折衷具合はAdorableも思い出す。ギターの音色が唯一無二ですね。こんだけ弾きまくってるのに清涼感あるのはたぶん音色のおかげかもしれないけど、この遠くで鳴ってる音を聴いてる感じはどことなく郷愁的で良すぎる。wipe氏のイノセントなボーカルもいい意味で崩れた雰囲気があって、「Javelin」の突っ走ってる感じとかすごく好きです。

先行トラックの「Hear I Stand」がもろにスロウコアな質感でスカスカで硬質なギターとドラムの残響で空間そのものの奥行きを音と音の合間で表現する曲で、シューゲやドリームポップの空間を満たす手法とは逆の、音数を減らした硬質なギターの残響、そっから炸裂する轟音はどちらかというとHum系列のヘヴィシューゲ。アルバム通しても至るとこから痛みを感じるようなスローペースのヒリついた曲が多くて前作とは全く違ったアプローチですがかなり良かった。

bandcampスロウコアタグより。アンビエント/エレクトロニカのトラックメイクをふんだんに使った音の隙間とキャッチ―な音色の抜き差しが絶妙な歌ものスロウコア、隙間だらけでもそこまで分離がよくないローファイな質感が暖かくて、バンドとトラックが分離し切ってない一個丸まった形として入ってくるごった煮感がメロディーの優しさとぶつかって90sUSインディーくらいのジャンクな親しみやすさがある。

再結成に驚くしかなかった。メンバーは変わらずEarly Day Minersでも知られるダニエル・バートンを中心にしてドラムはCodeineのクリス・ブロコウという驚きの面子。初期のSlint路線なのか中期のマス/スロウコアなのか解散直前のポストハードコアなのか・・・再生するとそれは20年のキャリアを感じさせる円熟しきった、中期~後期をミックスしたような、どの時期とも接続できるスロウコアに限りなく近いポストハードコア。色々そぎ落としたニュートラル状態で素をさらけ出してる感じがします。

アンビエントな色が強い長尺なナンバーで埋め尽くされたAidan Baker新譜はめちゃくちゃスペーシー、月面とか宇宙空間に放り出されただただ広大な闇に押しつぶされズブズブと飲み込まれ呆然としていたくなるような無重力を感じるダビーなスロウコア。不定期なドラムの残響がとても重くてこれが癖になります。
Midwife & Vyva Melinkolya - Orbweaving

こちらもwaveform*と同じくbandcampスロウコアタグ常連MidwifeがVyva Melinkolyaとコラボレーションしたアルバム。Aidan Bakerとはちょっと色が違いますがこちらも半分アンビエントと融合し幽体化したスロウコアバンドみたいな感じで、とにかく暗くてサッドコアという言葉を使いたくなります。ぼんやりと薄い膜がいくつも折り重なってドリームポップやシューゲイズの雰囲気もあって全部が曖昧にされた中今にも途切れそうに紡がれるボーカルが染みる。

最初の「Moonlise Kingdome」からシューゲイザー色強くてびっくりしたけどアルバム通してそういったわけではなく、「ブラックホール・ベイビー」はナンバガだったりスマパンだったり「2AM」はキュアー+スミスだったり、トディ曲の「Teardrops」はプラトゥリを思い出し、どの曲もエッジが効いていて雑にオルタナって呼びたくなる懐かしさがあって、Baby Acid Baby~Youあたりの新体制による硬質な荒々しさも残しながら初期を連想する要素あってすごくよかったです。声がめっちゃ調子いいのも驚きだった。
アイカツ! 10th STORY 未来へのSTARWAY

本当にありがとう。
これはART-SCHOOLじゃない方のルミナスの新曲で、この3人による新しい曲が聞けるとは思っていなかった上にあまりの素晴らしさに落涙。
Sign? Go! Dream!!
NARASAKI新曲。Signalize!!意識ということでジャケも似通っていて本当にぶち上がったしNew Order要素もかなり入っていて、10年前の第一話のOPという歴史的な曲と対になるのにも関わらずここまで渋い曲に仕上げて尚且つオマージュも散りばめられていて驚きました。個人的にLily Furyと並べて聴きたい。劇場版直後というのもあり色々と思い出して聴いていて涙が止まらないですね。
以上です。あとはBully、Narrow Head、Wednesday、Murder Capitalとか聞いてました。Mhaolっていうポストパンクも良かった。あとSwans新譜も。Iggy Popの新譜も初期くらいパンキッシュで驚きでした。Truth ClubとかSprainとか前々から好きなバンドも続々シングルとか出てて下半期も楽しみです。7月分だとPSP Socialがヤバかった。サーフブンガクカマクラ完全版はあんましっくりきてないです。今期はBLEACH見ます。