もう2024年の3月ですがやっていきます。
Blonde Redhead - Sit Down for Dinner(2023)

Blonde Redheadの9年ぶりの新作。00年台中盤での4AD移籍後の作品が有名で、ゴスやシューゲイザーの文脈でも聞かれるアーティストですが、自分の中では90年台のポストハードコア/ジャンクロック真っただ中のTouch and Goからリリースしていたイメージが強く、初期2作はSonic Youthのスティーヴ・シェリー主宰のSmels Like Recordsから作品を発表していました。90年代のアンダーグラウンドなシーンから耽美でゴシックなアートポップへと、ポストロック激動の時代で圧倒的な個を確立させ横断していったアーティストとしてのイメージが強いです。Smells Like時代の音源がちょうど2023年にリリースされているので聞き比べるのも面白いかも。今作9月リリースですがこの強烈に冷たい質感は冬にぴったりだなと思い、実際気温が低くなってからは肌感覚で非常にしっくりくる作品で、おそらく下半期最も聞いたアルバムになりました。M1のSnowmanから薄い半透明のカーテンを何重にもかけて視界をぼかしていくような、この中でポストパンクやクラウトロックを思い出す淡々としたビートを気が遠くなるほど繰り返し、深く深く内面の底まで落としてくれる非常に没入感の強い名曲。4AD以降の路線が完全に円熟し切ってます。気が遠くなるほど、とは言いましたが、実際には通して5分しかない事実に驚いてしまうほど陶酔的で、自分の視聴感覚とのズレにかなり衝撃を受けました。M6~M7のSit Down for Dinnerというアルバムタイトルを冠する2曲はミニマルな音の隙間、空白を単なる空白として聞かせないサウンドスケープはモノクロームな世界に少しずつ色をつけ情景を描いていくような非常に映像的な2曲です。カズ・マキノの唯一無二の歌声も強烈に刺さってきて、今作は明確に近しい人たちとの別れをテーマにした作品とのことですが、ただ単に暗いという言葉で片づけるわけにはいかない喪失感に寄り添ってくれる穏やかなアルバムだと思います。
活動30周年という節目にリリースされた今作ですが、最近KEXPの方で公開されたライブ映像がアルバム収録曲の冷たいイメージを全く損なわないまま、曲の熱量を上げていく様が見事に両立された圧巻のパフォーマンスで衝撃でした。とくに「Snowman」「Melody Experiment」の2曲はつい涙してしまう名演です。音源と比べてドラムが有機的になったのも大きいと思いますが、一度これを見るとアルバムを聞く視点もまた変わってくると思うし本当に素晴らしいので是非とも。
Truth Club - Running From the Chase(2023)

Truth Clubの2nd。2019年の1stも当時の年間ベストで上げたバンドで、前作ではまだ初期Dry Cleaningのようなポストパンクとインディーロックの折衷と言った要素が強かったですが、今作はエモ一歩手前といったノスタルジックな情感漂うギターロック色の強い作品に。収録曲全てが名曲です。アルバム通してどの曲にも徹底的に"くたびれた"雰囲気がずっと漂っているのが良い。このくたくたに疲れたボーカルと、音数を減らした静パートの噛み合わせはスロウコアと通じるところが多々あるし、そのままじわじわ熱量を上げていくアンサンブルはただ音の厚みと轟音でカタルシスを演出するのではなく、肥大化させたものを爆発させず、ガスを抜くように風通しよく穴を空けてしまう平熱のボーカルが強烈に自分のツボを刺激します。5th emo waveやエモリバイバルといった90sのハードコアから直接繋がる硬質な質感を絶妙に避けていて、轟音に至るシーンも多いですがシューゲイズのような空間的なものでもない、もっと物理的なガシャガシャとした密度のあるバンドの音圧は90年台のCastorらも思い出してしまいます。OvlovやHorse Jumper of Loveといった10年台以降のインディーロック/オルタナのラインから、Weatherdayのように日本のギターロックファンにも刺さりそうな作品で、90sのインディーロックや枯れエモからこういったジャンルを聞くようになった自分にとって、熱量を上げすぎない質感がすごく肌に合ったアルバムでした。

deathcrashの2nd。1年ぶりの新作で前作のSlintやCodeineを思い出すスロウコアライクな作風とは地続きのまま、寒々しく硬質だったサウンドスケープはLessというタイトルが示す通りより隙間、空間の間を強調するソフトで生々しいミニマルなものへと変化。その結果元々バンドの特徴であった穏やかなソングライティングが浮き彫りになりSlint~Mogwaiといったポストロックのラインからは外れてきた作品だと思います。目の前で楽曲が組みあがってく様を見ているような静謐なアンサンブルは決して轟音の前座として作られたものではないし、むしろメインは静寂の方にあるのではないかと、繊細な感情の動きや、痛みを、その情景を、よりハッキリと描き出すために選択されたものがこの静謐さなのだと思わされてしまうほど、美しい曲群に涙してしまいます。
リリース直後に書いた単発記事。こちらでもう少し深く掘り下げています。また今年の3月に音楽を聴く環境について / 車内音楽まとめという記事を書いたのですが、音楽を聴く環境が自分の視聴傾向を左右し音楽趣味を作っているという内容で、そして冬の肌寒さとマッチした、その季節に車内という密室で聞いたことで自分の聞く音楽の傾向が引っ張られていったという旨を話しているのですが、deathcrashに先ほどのBlonde RedheadやTruth Clubも確実にそこと一致した音楽だったと思います。
Sprain - The Lamb As Effigy(2023)

ロサンゼルス出身Sprainの2nd。元々2018年にリリースされた最初のEPはEarly Day MinersやDusterのような暖かいメロディーの王道スロウコアを真っすぐにやっていて、そして2020年セルフタイトルの1stでUnwoundとSlint~June of 44を掛け合わせたかのような硬質で捻じれたポストハードコアへと大きく変貌。スロウコアとポストハードコアが太いパイプで繋がっていることをまじまじと見せつけるような作風で、これを2020年にやるのかと心から震えました。そして2023年、今作The Lamb As Effigyで彼らは異形のバンドへと進化を遂げます。UnwoundのLeaves Turn Inside YouがSonic YouthのDiamond Seaを喰ったようなアルバムで、マッシブなSlintとも呼びたくなる前作譲りの硬質で強靭なバンドの芯を屋台骨としながら、重厚なストリングスや不穏なオルガン、美しいアコースティックギターの旋律を聞かせたかと思いきや、今度はそれらを一瞬で塗りつぶす耳を塞ぎたくなるような金切りノイズ、時折見せつける悲壮感にまみれた虚無の時間と、静寂とバーストがはっきりと対比的にあるわけでもない、ただただ居心地の悪い、どこか呪術的ですらあるモノクロームの万華鏡のような美しい音世界。感覚的にはP.i.L.のFlowers of Romanceも思い出してしまいます。8曲90分超えのボリューム、目まぐるしく動く世界観はとても軽い気持ちで聞き流せるアルバムではないし、聞きやすい作品だとも思いませんが、ここまで完全にブレーキがぶっ壊れたまま、自分たちの世界に行ってしまったものを体験できるアルバムは他にないと思います。M2のReiterationsは結構わかりやすいポストハードコア路線で、1stの地続きとして最も聞ける曲だと思います。M5のThe Commericial Nudeは(イントロは激しいノイズですが)スロウコア路線として圧倒的に美しい名曲。M6のThe Recliing NudeはZepのNo Quarterのようなカタルシスがあります。
SPOILMAN - UNDERTOW(2023)/COMBER(2023)


2023年5月に脅威の2枚同時リリースを成し遂げたSPOILMANの2枚。Touch and Goライクなポストハードコアから呪術的でおどろおどろしい未踏の境地に至った怪作HARMONYから1年、HARMONYの路線を受け継ぎながらMelvinsあたりも思い出すドゥーミーな香り、Blonde RedheadやShipping Newsにまで通じる不穏さを芳醇に纏ったCOMBERと、逆に1st2nd期を思い出すJesus Lizard路線を再び突き詰めたように思える、リズム隊のドライブ感と全身刃物のような鋭利なジャンクギターが全てを飲み込むUNDERTOWというそれぞれ明確に違う色を持った二作。決して二枚組というわけではなくそれぞれがコンセプチュアルな世界観を持ったアルバムで、どちらも合間にインストを挟むことで流れもしっかりしてますし、何より単発でライブアンセムとしてもとてつもなくかっこいいシンプルな名曲「Super Pyramid Schems」「Fantastic Car Sex」がそれぞれのアルバムで核として存在していて、そこに至るまでの導火線の如く張り巡らされたアルバム構成の妙も見事で本当に凄まじいバンドだなと実感しました。
このアルバムを皮切りに初の全国ツアーを行っていたSPOILMAN、昨年末の12月最後に東京の公民館を借りて入場無料でライブが開かれたのですが、かつて90年台にライブハウスではなくガレージや野外でライブしているアメリカのバンドの動画を数多く見てきた自分が、まさか生きてる内に同じような体験できるとは思ってもみず心から興奮しました。体育館という天然のルームリバーブに満ちたドラムの音も唯一無二でしたし、何よりメンバー全員が心から楽しんで演奏している様が伝わってきた。さらに驚きなのが当日サプライズでまた新しいアルバムがリリースされていて、2023年に3枚リリースという過密スケジュールには言葉が出なくなりました。
公民館ライブはこちらで公開されてるので是非とも。
単発記事の方でより掘り下げています。
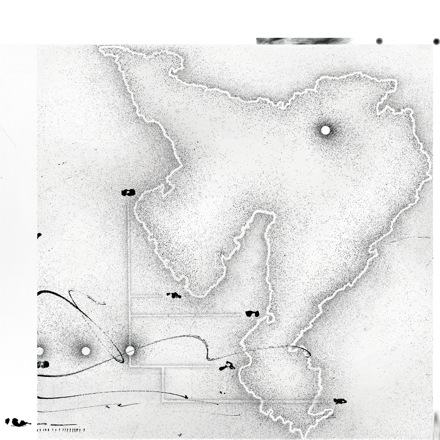
上半期まとめでも触れた5kaiの2nd。前作までは54-71やdownyも連想する円を描くような鋭い反復が主だったのですが、今作はそれを更に分解して自由な感覚で再配置したことで人力IDMのような音楽性に。相変わらずスロウコアと呼ぶにはマッシブすぎる線の細いポストハードコアで、アコースティックな色も見せながら今まで以上に"歌"を大切にしたアルバムに思えます。とくにそれはライブにおいて顕著で、生で聞くことで殺伐とした冷たい世界を描き出す演奏とは対照的な、すごくくたびれたボーカルがどこか暖かく、一見歪に見える今作の曲達も純粋に生活から零れ落ちてしまったものがあの形になってるだけなのではと、それほどまでに剝き出しの歌と最低限ながら力強い演奏は強烈に胸に刺さってきました。M2の棚という曲は2023年ベストトラックです。
PSP Social - 宇宙から来た人(2023)

PSP Socialの2nd。前作までのジャンクエモと呼びたくなる荒々しいハードコア色の強い作風からは全く想像できなかった新境地のアルバムで、音をごっそりそぎ落としゆったりとした時間感覚が漂う長尺のスロウコア5曲45分。日常の裏にいつ反転してもおかしくない非日常がある危うさを匂わせるような、すごく聞き慣れてるようで、でもどこか違和感が残る異界っぽさが仄かに漂う。硬質なスロウコアではあるんだけど、露骨な隙間を作るわけでもなく、そういったジャンルで一口に括りたくない、羅針盤とも通じる日本のバンドにしかない和の風情というか、日本語特有の優しい響きと牧歌的な雰囲気に満ちた作品。密室に閉じこもるのとは全くの逆、すごく自然に外に向けて演奏されている感じがする。このアルバムのインスピレーション元がPink Floydのおせっかいだというのも驚きで、おそらく本人達の中で独自のサイケデリックな感覚が昇華されこの形になったのだと思うし、自分の知らなかった一つの新しい解釈を見せてもらった気持ちになりリリース以降夢中になって聞いていた。
Pharoah Sanders - Pharoah(1977)

スピリチュアル・ジャズの大御所ファラオ・サンダース1977年作がデヴィッド・バーンのレーベルであるLuaka Bopより再発。しかもライブ音源を収録していて、リリースされた9月以降今に至るまでずっと聞いている作品です。彼特有の陶酔的に繰り返されるフレーズの反復の妙がよく出た3曲で、サイケデリックを通り越してチルの領域にまで足を踏み込みかけた印象もあるM1のHarvest Timeにおける、ギターとベースのリフレインの各レイヤー入り組みながら完全には重ならないよう宙に浮く音の配置は非常に繊細。この和音の心地よさに恍惚としてしまいます。そしてM2のLove Will Find a Wayにおいては、初期作で確立させたコルトレーン以降のスピリチュアルな作風を一回薄めてアフリカンな色を強くしたWisdom through Musicを継承したような1曲で、肩の力抜いて聞ける反復のセッションと、クライマックスにおいて体の奥底から振り絞った生命力そのものを見せつけるかのようなダイナミックなサックスソロはしっかり心を揺さぶってくる。彼の作品って結構気合入れて聞くイメージがあって代表作の「Tauhid」や「Karma」は映画一本見るくらい大作ですが、このアルバムは地に足のついたグルーヴィーなリズムを根幹としつつ、それを構成する音色がどれもこれも浮遊感のある聞き疲れしないもので構成されていて軽い気持ちで流しやすい。生音感が強く、密室で聞いてる印象を加速させるリズム隊の録音もめちゃくちゃマッチしていると思います。それでいて腰を据えて聞いてもしっかりフックのあるおかずが散りばめられていて、じっくり世界観を味わえば味わう程ラストのサックスソロにおけるカタルシスも増すという、こういった、聞き時を選ばないという点も愛聴盤になった大きな要因かと。ファラオ・サンダースをこれから聞きたいという方にもおすすめです。
最近はディスクユニオンへ行っても音源よりも中古音楽雑誌コーナーを先に見に行くことが多く、その中で買った2003年のレコード・コレクターズにおけるファラオ・サンダース特集をガイドにして聞いてました。ジャズは歴史が長いのもあって書籍やインターネットのブログまで非常に広く資料があり、そして自分は音楽を聴くこと自体と同じくらい、もしくはそれ以上に"音楽に関する文章を読むこと"自体が好きであると気づきます。もう最初とは順序として逆なのですが、音楽に関する文章を一つの読み物、創作として楽しみ、そのサントラとして音楽を聴くというわくわくを最も感じた一年でした。
Sly & The Family Stone - Fresh(1972)

2023年は退職や引っ越しに伴って生活ががらりと変わりインターネットが使えない時期が長く、サブスクで新譜を追う頻度が激減。ディスクガイドやブログを参照し気になった音源を購入したり、久々にCDレンタルを利用して旧譜を聞くことが主となりました。その中でファンクにハマり、資料を元にしながら大御所を一通り聞いていたのですが、今になって改めて衝撃を受け一年を通して最も再生したアルバムがこのFreashになります。音数の少なさで立体的に浮かび上がる、すぐそこの空間に音が固形として存在していて、触れるんじゃないかと錯覚してしまうほど巧妙に配置された各パートは、M1のIn Timeの再生数秒から胸の奥をぐっと鷲掴みにされたような魅力がありました。カタルシスを"ズラす"ような美学がとにかく詰め込まれたアルバムだと思います。代表作でもある前作の"暴動"で培った、リズムマシンを使ったミニマルなビート感、このシンプルな反復の心地よさを、土臭いソウルから距離をとり新たに追求したような、ドラムもベースも、現代におけるポストプロダクション的な、隙間を利用してスタジオ作品としてこう聞かせたいっていう音の配置を重視したフレージングなのではないかと思えてなりません。後ろから纏わりついてはすぐ消えてしまうと言った感じで、そんな中ツボのみをつく控えめなホーンセクションも体の奥底を揺さぶってくる。曲の、平熱を装うクールなテンションとは反対に、聞いてるこちらはその強烈なファンクネスにどんどん熱量が上がり踊らずにはいられない。ある程度地盤ができてきた今だからこそ好きになれた作品で、2023年出会えた中で最も大切な1枚です。

ライブ会場を中心に販売されたOGRE YOU ASSHOLEの新譜で(9月にサブスクでも聞けるように)、OGRE YOU ASSHOLEは普段からライブに通ってるバンドですが最近のライブはファンク色が強く、余白をたくさん残すことで骨組みを露出させたスタジオ盤の作風は実際にルーツにカーティス・メイフィールドを上げているところからも重なるところが多々あります。とくに2017年作の「ハンドルを放す前に」の音数を絞ったミニマルな作風はSlyのFreashを聞いたときにフラッシュバックした1枚です。今作はNeu!やCluster、CANといったバンドのオマージュが散りばめられたクラウトロックを地で行く作品で、スタジオ盤のオウガとしては珍しく電子音のシーケンスがずっとメインに据えられていて、それ故にそのシーケンスと並走するドラムの強烈なグルーヴが今まで以上に際立った作品でした。ライブの熱量のピーク直前とも言える瞬間をうまいことパッケージングした作品にも思えて、平熱を保ったまま永遠に踊り続けられるアルバムになったと思います。

Squidの2nd。オウガの家の外と並んで自分の上半期を象徴する2枚です。今作はグルーヴィーな1stの粘り気の強いビート感はそのまま、ノイズやパーカッション、ホーンセクションといった曲を彩る要素をどんどん足していったにも関わらず、エッジの効いた各パートの音の隙間はしっかり見える、アンビエンスと固形化したアンサンブルのソリッドさを両立させた作品で衝撃を受けました。今作ジョン・マッケンタイアがプロデュースをしていて、セットで1stも聞き返したところ両作ともポストパンクという側面よりクラウトロックやファンクの遺伝子に強烈に惹かれます。Squidはパンクシーンから出てきてWARPからリリースした経緯や、元々ライブハウスでファンクを演奏していたという経緯が自分の中で!!!と重なり、!!!自身がハードコアシーンを出自としながらWARPへ移行したという流れも完全に同じで、このルーツに接近したい、自分が聞いていて最も心地いい瞬間、その感覚のルーツとなる部分にもっと切り込んでいきたいという気持ちからファンクへと興味が向いていきます。その中でレコードコレクターズのソウル/ファンク特集やFunk Of Agesというサイトをガイドにしながら、先述したFreashの冒頭の流れに繋がっていきます。

下半期は新譜チェックの傍ら音楽を掘る時間はほぼファンクを追っていて、ポストパンクやAOR周りからかつて聞いたものより前の、70年台を中心にJBのライブ盤やコンピ、P-FUNK諸作といった王道を順番に聞き、JBからP-FUNKやSlyの人脈を辿ってオハイオ・ファンク、ベイエリア・ファンクに傾倒し、80年台に移行しながらZappやPrince諸作を主に聞いていました。とくにPrinceはかつて苦手意識すらあったのが、Slyを経過した上で聞くとミニマル路線でリンクする部分が非常に多く、ようやく和解できた感覚があり上記のオウガの流れにもリンクします。元々FunkadericのファンだったのもありP-FUNK諸作もしっくりきて、王道ですがMothershipは上記のSlyのFreashと並んで2023年かなり聞いたアルバムです。Freashと通じる聞き方も多数できる作品だと思っていて、音数の少なさ、曲自体はミニマルな反復の中でもねっとり絡みつくような各パートのグルーヴ、そしてその中でも徐々に熱を帯びていく感覚はParliament独自のもの。ジャンル概念自体がまだできたばかりで曖昧だったのもあると思いますが、SlyやPariliamentの70s中期の作風は本当に混沌としていて、これが一つのジャンルとして共存していたのかと聞き進めるのがとても楽しかったです。P-FUNKやSlyの次にハマっていたバンドがOhio Players、オハイオファンクと言えば後のSlaveにも繋がっていくバンドですが、P-FUNKへと合流していくジュニーがコンポーザーを担っていたウエストバウンド時代がとくに好みで、リズム隊の周辺をねばつくように絡みつくホーンセクションやオルガンはジャジーな色も強くよく聞いてました。ジュニーのP-FUNK期だとOne Nation Under A Grooveがベストです。Ohio Playersはジュニー脱退後も好きなアルバムが多く、後期だとSkin Tightをよく聞いてました。

バンドリシリーズは一切見たことなかったんですが、MyGO!!!!!がenvyっぽいという意見をツイッターで見かけて興味を持ちアニメを視聴したところ、第一話冒頭数分からあまりにも不穏でギスギスとしたバンドの崩壊を生々しく映していて一気に飲み込まれました。冒頭で触れたenvyのようなポエトリー主体のエモ前夜/ポストロックの雰囲気まで感じる楽曲もすごく肌に合いますし、アルバム収録曲の音一会といった楽曲はくだらない一日のようで昨今の国内エモシーンと呼応する部分も感じられ、そういったミッシングリンクから背後に激情やまだギターロックっぽさがあったTen Rapid期のMogwaiも連想してしまいます。アニメ本編もバンド作品として、作中で曲が生まれ、メンバーが肉付けしてできあがってくプロセスを丁寧に描いているので、そういった楽曲が実際にライブで演奏されていく過程にカタルシスを感じたり、人間関係の軋轢からくるバンド崩壊寸前のところから、その傷を癒すように新しい曲が生まれ再生していく様が描かれていてかなり衝撃でした。従来のバンドリと大分毛色が違う作品らしく、だからこそ肌にあったのかなとも思いますが、今後のリリースも楽しみです。
littlegirlhiace - INTO KIVOTOS(2023)

2023年にリリースされた4枚目のフルアルバム。ここ数年の集大成のようなとんでもないアルバムになったと思います。個人的にbandcampや物販にイラストとして参加させていただきました。先日単独記事を公開したので是非とも。

Spotifyの年間レポートだと、2023年最も聞いた曲がこのアルバムの1曲目にあたる電子の砂漠でした。硬質で冷たいギターの感触と、どこかくたびれているようで、内にある熱いものが自然とにじみ出てきたような言葉の並びに強烈に胸を打たれてしまう。00年台ギターロックっぽい表情を見せる瞬間が多々あって、個人的なルーツからも懐かしくなってしまいます。上半期まとめでも触れたアルバムで一年を通してよく聞いてました。第12話はやはり何度聞いても共感してしまう名曲。
以上でした。順不同です。今年は生活的に大きな変化が多くあまり音楽を掘ることがなくなったのですが、だからこそ、例年の自分だったら選ばないであろう選盤ができたかなとも思います。旧譜にハマり、アーカイブ化された資料を元に"面"として音楽を聴くことが増えるにつれ、こういった年間ベストを書く意義や、新しい音楽を年内に聞くことについて色々考えてしまいますが、こういった記事自体が将来一つの面として楽しめる日もくるんじゃないかと思います。
あとは2023年、終盤はほぼ同人誌の制作をしていました。イラスト集+音楽ZINEで音楽ZINEの方では主にスロウコアに関して書いてます。元々、イラストの作風と音楽の方向性を合わせる予定はなかったのですが、作ってく内にジャンル関係なく通じる世界観が自然と滲み出てきて、自分の見てる世界のレンズがどういう色をしているのかわかったような気がします。気になった方は手に取っていただけると嬉しいです。
関連記事