
2001年結成。初期の頃は90年代のUSインディーをベースにしたようなロック~ディスコパンクシーンとも比較されながら徐々にサイケデリックへと傾倒しAORやクラウトロック、プログレの空気まで入っていきながらソフトサイケな歌ものへ。音源とライブでの演奏を完全に分けていて、ライブではアレンジも多くグルーヴ重視~轟音まで大化けします。
一時期狂ったようにライブに通いまくってました。かなり多方面から楽しめるというのもあり1stから順に追っていきます。
初公開 2021-02-19
アルバムリリースに伴い更新 2024-10-23

セルフタイトルの1st。元々OGRE YOU ASSHOLEというバンド名の由来はかつてメンバーが敬愛していたModest Mouseの来日ライブに行ったとき、メンバーにサインをねだったところ書かれた文字(もうほぼラクガキみたいなものではあるけど)をそのままバンド名にしてしまったというエピソードがある。1stアルバムということでそんなModest Mouseを強烈に思い出すローファイな作品、というか歌い方までも近いと思わせる瞬間も多々あって少し微笑ましいが、あちらと比べるとジャケット通りかなり不穏な雰囲気が漂っている。
メロディーも声もキャッチーで普通に00年代の邦楽ギターロックな流れでも聞けるアルバムだとは思うけど、後期の本格的なサイケデリック・ロックとかとはまた違った、独特の得たいの知れない危うさとも言える後期とは違ったサイケ感が滲み出ている。「タニシ」「また明日」という今でもライブで聞けるナンバーも収録されていて、この辺もメロディはポップでもUSのローファイ経由のヘロヘロな音像とボーカルによってくたびれた情緒が漂っててとても良い。「ロポトミー」では今からは考えられないような苛烈なシャウトが聞ける。タニシでのツインギターの絡み合いは割りと後にも通じるかも。オウガにしてはガシャガシャとした荒々しい録音も特徴的。
割とUSインディーライクな作品ながらこの頃からドラムは後を想起させるミニマルさが表出していて、これがインディーロックとして聞くのなら結構浮いているんだけど、それが逆に味、というか一貫したバンドの個性になっている感じが良い。というかドラマーだけ当時からプログレ~クラウトロックとかポストロック嗜好だったというのもバンドの出自や後の音楽性を考えるととても大きかったのだと思う。

1st後に出たEPで前作と比べたら音もキレイになり雰囲気もポップに。というか1曲目からアコースティックで始まるオウガ随一にポップな曲で、前作から来るとびっくりするんだけど、捻くれた曲展開というか、予想外なとこから飛び道具が飛んでくるのは相変わらず。音色の透明感ある艶っぽさはネオアコを想起するし、前作と比べるとポストパンクっぽいアルバムかも。
MVもある初期の代表曲アドバンテージはこれまたおそらくModest Mouseっぽい疾走ナンバー、2ndに収録された版のLoungeっぽいが、それをめちゃくちゃ肉付けしてよりドラマティックにした感じで、この頃のUSインディーを咀嚼した彼らの王道のロックサウンドはこれで完成されちゃってる気もするし、このまま次作の1stフルアルバムへも繋がっていく。後に難解になってくことを考えるとストレートにクールがギターロックやってた唯一の曲ではないかと思う。表題曲でもある平均は左右逆の期待はドロドロと溶け出すような怪しいギターのトーンがかなり癖になる。

この頃のOGRE YOU ASSHOLEの集大成とも言える名盤。フロントマンである出戸学が度々影響を公言するTelevisionの色がフレーズや音色からもかなり濃く出てきて、Marquee Moonで見られる単音ツインギターの絡み合いを完全に昇華しその上で歌ものインディーロックをやった大傑作。リフとリフを反復しセッションを続け、どんどん新たなギターフレーズが登場しドラマティックに展開していく・・・というのをわかりやすく3分~5分のサイズでコンパクトにしたような曲が多く、ギターのフレーズを耳で辿るだけでもこれがかなり楽しい。とくにM5のサカサマは必聴。M3のバックシートの後半のギターワークも泣ける。
Modest MouseというよりBuilt To Spillっぽい感じがかなり出ていてオウガの中で最も人懐っこいアルバムにも聞こえるし、でもやっぱりちょっと無機質な感じになっちゃうのは出戸さんの声と掴みどころのない歌詞、情報量の割にアンサンブルはスッキリしてて隙間がハッキリ見えるってのがあるんだと思う。今では別物に変貌してしまったライブアンセムの「フラッグ」の骨組みとも言える原曲もここ。この単音メイン故の線の細い各パートの骨格が露出してる部分は前作に引き続きポストパンクっぽさもあるし、当時The RaptureやFranz Ferdinandと比較されていたのもちょっとわかる。

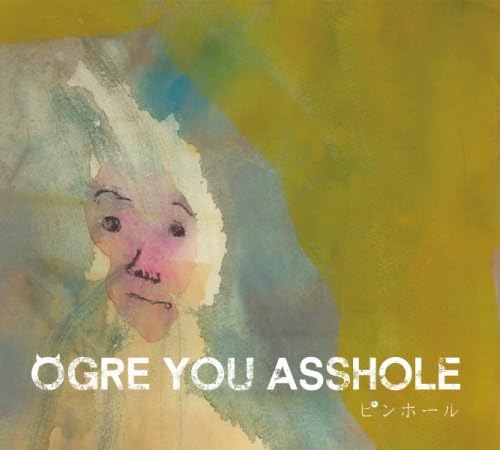
メジャーデビューシングルのピンホールと同時期のEPしらない合図しらせる子の2作。デビューということでピンホールは非常にポップで最も一般受けする曲で、Helsink Lambda Clubがオマージュしている。この頃からプロデューサーとして石原洋、エンジニアに中村宗一郎というゆらゆら帝国を手掛ける二人と手を組んだバンドの重要な転換点。
今作、後期のどんよりとしたサイケデリアとはまた別の、多幸感あふれるメランコリックなサイケデリアが結構滲み出てきてて、この辺はおそらくThe Flaming Lipsが由来になっている。石原洋と最初に会ったときこんなことやりたい、ていうモデルとして挙げたバンドの一つだったとインタビューで直接公言されてるバンドでもある。ギターの音も大分くぐもった乾いた質感になってきて、これも後期への兆候な気がするけど音自体はまだまだUSインディーオルタナの範疇な感じがする。ラムダでのドラマティックなギターロック路線と近いひとり乗りはガチ名曲。
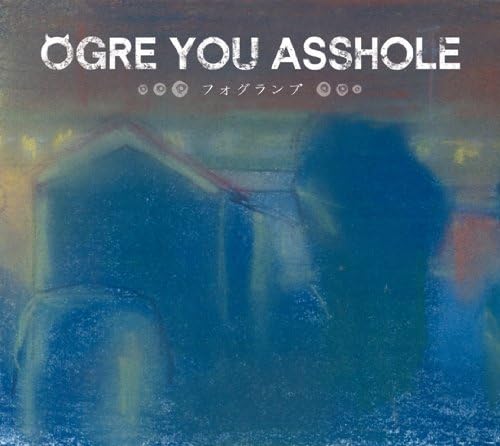
前作と同じく単音ツインギターのアンサンブルによる歌もの・・・の延長ではあるんだけど、そこまでキャッチーではなくなっていて後期のサイケデリックな空気がぼんやり出た全体的にどんよりとしたアルバム。尚且つその空虚さを伴ったまま、まだギターロックの範疇という異色作でもあり、後期のサイケ期を期待して聞くと物足りず、逆にアルファベータを期待して聞くと重くなりすぎな感じもある。ただこのどっちつかずだからこそ、今作が一番好きって方も結構いそうな唯一無二の時期だと思う。
アルバムを象徴する現在においてもライブ演奏されがちな名曲がアルバムラストを飾るワイパーで、一つのリフを繰り返してくうちに徐々に絶頂へ向かう・・・という淡々としたアンサンブルの中、じわじわと変化をつけていくかなりミニマルな楽曲で、前作にあった目まぐるしくドラマティックに展開していくラムダ路線とはまるで違った展開を見せる。この反復の繰り返しによるカタルシスは現在におけるサイケ以降のオウガ、それこそクラウトロックやダブ、ソウル/ファンクの時期の片鱗が出ていると思う。ジョニー・マーがオウガを指して「CANを早回ししたようなバンド」と例えたことがあるんだけど、時期と音的にたぶんこのアルバムだろうなぁ。

2010年リリースの名EP。フォグランプと並び丁度中間、録音の質感は全体的にふわっとしてるけど、リードトラック「バランス」がしらない合図しらせる子で出てきてたThe Flaming Lips歌謡の完成系とも言える名曲。たぶんオウガ屈指のポップさを誇っていてその印象のままあっさり聞けてしまえる。MVもチャーミングだし。
収録曲のタンカティーラはキラーチューンでフォグランプと比べると全体的に外に開けた、親しみやすい歌やリフ含めかなりポップな雰囲気があるけど、この明るさ、今までとは違いシュールさを伴ったもので、深読みすると少しだけ不気味に感じるような・・・という、ちょっとだけ毒の入った明るさだと思う。ジャケやタイトルもそうだし、何よりギターやシンセのトーンが今までと違って実態がないようなぼやけた感触があるし、後のサイケ~AOR路線が垣間見える。

2011年、震災を挟んでリリースされた衝撃作。こっから完全に今までの音楽とは別次元に行ってしまった感じがあり"USインディー"的な聞き方をすることはほぼできなくなってしまった。石原洋+中村宗一郎というかつて90年代にWhite Heavenを率い、00年代ではゆらゆら帝国をプロデュースしていた二人と組んだことで完全にサイケデリック~クラウトロックといったあの乾いた音楽へと変貌。自分は後追いだったけど、リアルタイムで追っていた人は一定数ふるいにかけられたのではないかと思うが、オウガ自身もマンネリ化を感じていたらしく、ライブのアプローチ含めガラリと変化を求めたというのがすごくストイックで自分たちの音楽を追求していくことに対して真摯ですごいなと思う。
homely、もう最小限のビートを刻む淡々としたギター、ドラム、ベース、そこにプログレ~クラウトロック的な効果音が飛散しながらミニマルな繰り返しの中で虚ろに踊るような、そこにゆらゆらとボーカルが浮遊していて今まで以上に淡々としている。歌詞も今までは意味があるようでないような単語をハメ込んできたバンドだったけど、「居心地の良い、悲惨な場所」をテーマに「ここから出ることはできない」と言う息が詰まるような閉鎖的な空気に包まれていて、統一感のある録音も含め完全にコンセプトアルバム。そもそもこの音楽性自体が、今までの作風の地続きではなく"描きたい世界観に合わせて音を選択した"ということで、今作からライブとスタジオアルバムを完全に切り分けるように。homelyは空虚な世界観がしっくりくるとのことで80sのAORをピックアップし、明確にSteely Danなどをリファレンスに挙げている。
最初聞いたときこの空気にやられて非常に重苦しかったんだけど、ライブで大化けする「ロープ」「フェンスのある家」辺りのキラーチューンの原型も収録されてて、乾き切った録音により空虚な印象を抱くが、よく聞くとメロディーはちゃんとキャッチー。ロープはかなりクラウトロック的、フェンスのある家はAORとの繋がりも感じれるホーンセクションやファンキーなベースラインが曲の虚ろさと対照的で不思議な魅力がある(それが怖さでもある)。「ライフワーク」はブルーアイドソウル感が強い新機軸のポップなナンバーでBlow Monkesyもチラつく。やっぱりかなり振り切ったアルバムだけど、これらを再編集、より肉体的になったworkshopというアルバムが後に出るため、今作がしっくりこなかった人には是非オススメしたい。後から聞くほど発見の多いアルバムだと思う。

100年後。前作の終末感を引き継ぎつつ、直接的に終わりを表現せずに100年後という"終わった後"を当てはめるのはかなりオウガらしいなと思う。個人的に最初に聞いたときはついにさっぱりわからなくなってしまったアルバム。インディーロックやポストパンク、オルタナという自分が聞き慣れたロックの枠から完全に外れたように感じてしまった。前作に引き続き完全にサイケデリック・ロックに傾倒、後のペーパークラフトとまとめて三部作と言われているけど、かと言ってhomelyとも大分趣向が違う。録音のふわっとした質感くらい?前作の方がもっとわかりやすく踊れるグルーヴが強いアルバムだったけど、今回今までで一番歌の比重が大きい。あと音への没入感。M1の「これから」イントロからもだけど、全体通してPink Floydっぽさもある。音を鳴らした後の残響が着地せずに地続きに浮遊し、ぼんやりと広がってくその幽玄な世界観に浸るといった作品。めちゃくちゃメロウ。M2の夜の船は今作を象徴する和製AOR。同路線の記憶に残らないも泣ける。M3の素敵な予感は後にドロドロのダブへと変貌しライブの定番へ。実際に2012年当時のライブを見たことはないんだけど、現在オウガのライブアレンジは非常にダビーな色が強く、このアルバムが割と起点になったのではないかと思う。

ジャケットが素晴らしすぎる。homely、100年後から続く三部作では個人的に一番好きなアルバム。今までのオウガってミニマルとメロウのコンセプトがそれぞれ別で存在していたと本人達も語っていて(おそらくhomelyがミニマル、100年後がメロウということだと思う)、それらを共存させた音楽性を目指し「ミニマルメロウ」をコンセプトにアルバムを作ったらしい。ということで結構双方の作風を引き継ぎつつポップになっていて、この三作では一番とっつきやすいアルバム。
ライブの定番であるM2の見えないルールはhomely路線の無機質なダンスナンバーの完成形。クラウトロックから来るであろう淡々としたビートを、"反復"という共通点を軸足にしてファンクの手法で再構築したかのような、ここまでやってきたOGRE YOU ASSHOLEのスタイルが一つの点に集約した名曲。David BowieがStation to Stationで行った白人流のファンク、ブルーアイドソウル前夜のサウンドをオウガなりに解釈したような雰囲気もあり、明らかにそぎ落とされた録音だけど、ライブにおいてはテンポを上げよりアグレッシブなライブアンセムへ。爆踊りできる。M4のムダがないって素晴らしいはギターではなくドラムとパーカッションが主格となる"リフ"的なものを担っていて、そこにキャッチーなメロディーが乗っかる、CANのTago Mago収録にMushroomやHalleluhwahが好きな人にはたまらないと思うし、ミニマルメロウってこういうことかと反復と歌のバランスが絶妙な塩梅で成り立ったクラウトロック歌謡。坂本龍一~David Sylvian辺りもちょっと思い出す。そして最終曲「誰もいない」のアウトロはhomelyの1曲目「明るい部屋」へと繋がる粋な演出も。三部作の最後として申し分のない名盤。
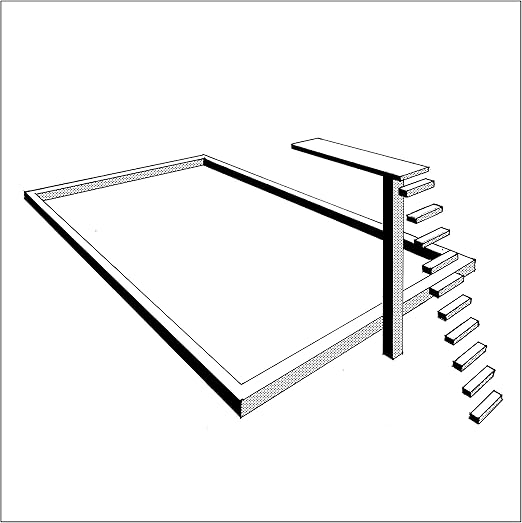
セルフプロデュースに移行した作品で、前作以上に演奏の音数が少なくミニマルに振り切ってるようにも感じるけど、そんな中でも三部作で会得したファンキーなグルーヴは健在。曲の隙間が増えたおかげか楽器の音一つ一つがよりはっきりと聞こえるし、何より固形っぽく鳴ってて今作にしかない点描のグルーヴがある。M3のなくしたはソウル/ファンクの感触でかなり踊れ、密室っぽい雰囲気と、少ない音数で体を揺さぶられるという意味でもSly & The Familly StoneやCurtis Mayfieldを思い出す。
そして「ハンドルを放す前に」「あの気分でもう一度」は要所要所でフレーズ一本で曲の印象全て持ってくようなキャッチーな場面が忍ばされていて、本当に些細な変化でも、ただでさえ普段がミニマルのため極小→小という動きで大きなカタルシスを得られてしまう。聞けば聞くほど空っぽな心地よさの奥にドラマティックなものを見出せる、homelyとは違った意味で一見シンプルだからこそ底が見えない、聞くたびに発見、及び自分自身に変化があるアルバム。個人的にあの気分でもう一度はベストトラックに上げたい。歌がすごく表情豊かで、演奏と掛け合うような侘び寂びの言葉にグッと来てしまう。音源だとスカスカな分ライブバージョンの広がりのある音響でメロウへと大化けするし、隙間が多い分各フレーズのぐにゃっとした感じはオウガのライブ特有のダブ感覚の片鱗を楽しめる。

ミニマルなソフトサイケで、結構今までのアルバムの中でもとくに歌の要素が強いかも。でもって三部作程重くもなく、あっさり聞けるシンプルなバンドアンサンブルはどことなく風通しが良い。今までの音の引き方とはちょっと違い、音の規模、世界観そのものが縮小されてて、引き算で作ったというよりは、すぐそこで鳴ってる言葉と歌がありのまま出てきたみたいな印象を受ける。
順を追って聞くとペーパークラフトで突き詰めた「ミニマルとメロウの共存」が最も自然な形で出てきてるアルバムだと思う。ペーパークラフトはミニマルなビートとメロウな歌、というとっつきやすい共存だったけど、今作はもっと、歌そのものにも、演奏一つ一つのニュアンスを取ってみても、ミニマルでありメロウである。空っぽなのに暖かみがある。歌詞も対象物がほとんど出てくることなく現象、状態を示す言葉が連ねられていて、石原洋が今作を「さっきまで誰かが"いた"ような、座っていた椅子の温もりが残っている」と捉えていたのもかなり納得。すごくラフで自然体で作られた感じもあるんだけど、コンセプトアルバムっぽい深読みもできてしまう。
そしてM3のさわれないのにはオウガの持つ無機質ながら、体を動かしたくなるファンクネス、三部作で多かった"反復の手法"とはまた違った形で、あの要素をうまくポップソングとして聞ける形に落とし込んでいて、グルーヴはそのままちょっと歌にも寄せた雰囲気が新しいファン層もガッツリ掴めそう。あとM2の朝は三部作以降のオウガの新しい変化を象徴する最重要曲といっても過言ではないのだが、あくまでライブ、そして別でリリースされたリミックス企画の流れも含めたものになっていて、本当の"素材そのまま"な音源だと割と小ぢんまりとしている。朝についてはworkshopに関する独立記事について再度触れていきたい。

2023年リリースの4曲入りEP。今までのオウガの作品では最もビートミュージックとしての側面が強く、スタジオ盤のオウガとしては珍しく電子音のシーケンスがずっとメインに据えられていて、それ故にそのシーケンスと並走するドラムのグルーヴが今まで以上に強烈に際立っている。低音もいつもより効いてるし、今回のギターは超ファンキー、立体的なドラムのビートも今作ほんとに凄まじく、全部合わせてめちゃくちゃ踊れる。とくに連作になっている「待ち時間」「家の外」はライブの熱量のピーク直前とも言える瞬間をうまいことパッケージングした雰囲気があって、音源の平熱感とは裏腹に聴いてるこちらはとんでもなくぶち上がってしまう、この曲のテンションによって蓋をされてるにも関わらず我慢できないほど体を揺らしてしまう、かなり独自の感覚になる。「ただ立ってる」はClusterのZuckerzeit風、そしてラストの「長い間」はHarmoniaやミヒャエル・ローターだと思って聞いていたら、歌が入ってきたところでCANのOh Yearと同じメロディーが飛び出てきて笑ってしまった。徹底してクラウトロック愛に溢れた作品。

2024年現在最新作となるアルバム。オウガはライブでのダビーな音響処理が音源とはまた違った心地良さがあるのだが、先行公開されたM1の偶然生まれたからそのイメージと重なってくる。徐々に体が音に埋もれていくような心地いいダブ風味の一曲(最初はもっとダブ色が強かったのを音源になる際に抑えたらしい)。オウガらしくとても隙間が映える。前作の家の外から引き続き今までで最もファンキーな作品だと思っていて、「お前の場所」「影を追う」はもうイントロにおけるベースラインと絶妙にツボだけをつき体を揺さぶるギターの差し引きからストレートに踊れる。三部作から感じたAOR~ブルーアイドソウルな作風からもう少し時代を進めて、今回は先行トラックだった「君よりも君らしい」の固形っぽい音のシンセのリフレインはぶっちゃけDuran Duranくらいまで思い出す。BrickやSlaveみたいな黎明期のディスコ、そこと直結する80sポップを淡白にしたようなソウル感覚が昇華された感じがすごく良い。ブルーアイドソウルからクラウトロックへ接近って意味ではまたしてもDavid Bowieを思い出してしまう。例えるなら三部作がStation to Station、家の外~自然とコンピューターはLowみたいな。
そしてクラウトロック色も今作強くて、ペーパークラフトと同様"反復"というワードを軸にHarmoniaやClusterの音でソウル/ファンクをやることで、グルーヴの骨格は残したまま土臭さを漂白したよう雰囲気があり、アナログシンセのフレーズやループにしっかり生演奏のような暖かみがある。ゆったりとしたファンクネスがビートミュージック的だった前作と対になってる気がするし、新バージョンで収録された「家の外」はとても象徴的かと。
以上でした。後はライブアルバム・・・というよりはライブ音源を再編集した「workshop」についてですが、個人的にオウガの最も大きな魅力が詰まってる三作だと思ってるので別記事にて触れていきます。