先日新譜をリリースしたばかりのFACSのアルバムと、フロントマンであるブライアン・ケースが在籍していた90 Day Men/Disappersの全アルバム感想記事。元々90 Day Menはdiscographyでいくつか書いていたのを再編し大幅追記、とくに以前書いたときはbandcampやサブスクの配信もなかったので聴くこと自体難しく、一昨年Numeroによって全音源再発されたのも大きい。先日素晴らしい来日公演もあったので今回改めてまとめていきます。
90 Day Men - 1975-1977-1998(1998)
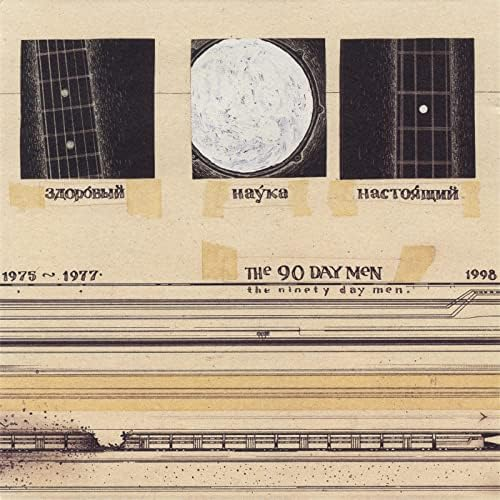
ポストロック名門Temporaly Residenseから98年にリリースされたEP。90 Day Menは元々ギター及びボーカルであるブライアン・ケースを中心とした3ピースバンドが母体になっていて、今作からマルチプレイヤーのロバート・ロウが参加し4人体制となってからは初の作品。プロデュースはアルビニのスタジオに在籍したグレッグ・ノーマン。バンドのキャリアの中では最もストレートに熱くなれるポストハードコア。M1のMy Trip to Venusはイントロから聞いてて不安になるような不協和音を生かしたフリーキーなギターサウンド、初期June of 44~Slintを連想する変則的なマス寄りジャンクサウンドでThe Exも想起する。M5のHey, Citronella!は6分超にわたるドロドロとした混沌なバンドサウンドを聞かせていて、3rd以降見せるサイケデリアの片鱗がこの時点で既にある。ちなみにTaking Apart The Vesselという96年頃に制作された自主製作時代の音源が、Numero Groupの再発によって聞くことができるように。こちらはストレートにTouch and Go/Dischordの影響下にある音でこれはこれでめちゃくちゃかっこいい(Taking Apart The Vessel ‑「Single」by 90 Day Men | Spotify)。
90 Day Men - (It (Is) It) Critical Band(2000)

Southern Recordsに移籍しての1stフルアルバム。Southern Recordsはバンドと交流が深かったティム・キンセラのJoan of Arc、そしてJune of 44やCodeineにも在籍したダグ・シャリンによるRex及びHiMの作品を多数リリースしていて、2000年前後のポストロックシーンを象徴したレーベルだと思う。前作に引き続き録音はグレッグ・ノーマン、彼もSouthern Recordsの作品に多数関わっている。今作から活動拠点をシカゴに移し、キーボードとしてアンドリュー・ランサンガンが参加。前作EPで見せたジャンクなギターサウンドはギュッと凝縮され硬質でソリッドなものになり、循環するギターリフを中心とした予測不能の曲展開、ほんのり香るジャズ要素はKing Crimsonを思い出し、鋭利なリフと構成の妙、バンドのジャム感はDon Caballero/Sweep the Leg Johnyといったインスト系マスロックとのリンクまで見えてくる。故に2ndや3rdと比べたらまだハードコア系譜のポストロックとして聴け、M1のDialed In、M8のJupitar And Ioに関しては渦巻くセッションにスポークンワーズを載せるというスタイルでJune of 44~Slint直系の遺伝子をまだまだ強く感じる。静→動のコントラストではなく、全体で変化し続ける流れや構成で聞かせる曲が多いのだが、M2のMissouri Kids Cussはストレートに真っ向からノイズに飲み込んでくるカタルシス満載の名曲。怪しく耽美なM7は次作やDisappiearsの布石感もある。2nd以降の異形な音楽性の方がバンドの特異性が際立っているが、まだまだポストハードコアの色を残した今作もすごく良い。個人的にポストロックという大きな単位で見ても確実に上位に入る作品。
90 Day Men - To Everybody(2002)
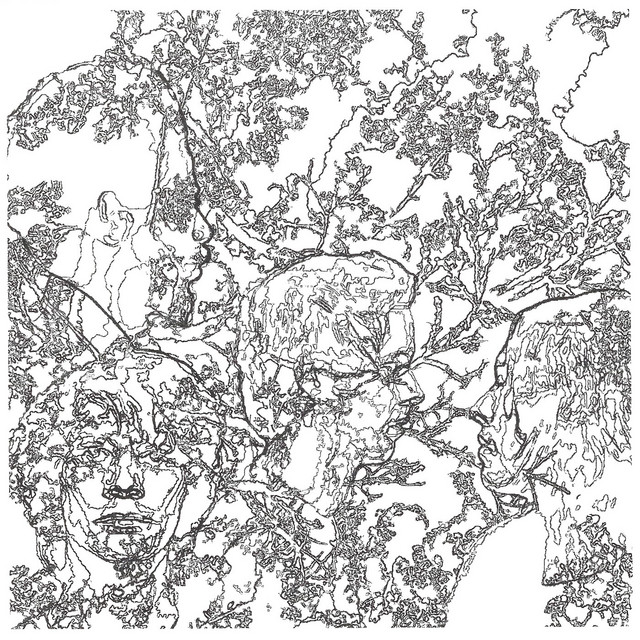
2002年にリリースされた2nd。ポストロックという不安定なジャンルの枠を更に飛躍させてしまったと感じるほどつかみどころがない、これまでの90 Day Menからは想像できなかった新たな景色を見せてくれる快作。アルバム開幕のI've Got Designs On Youではもう一人のボーカルであるロバート・ロウのハイトーンボイスとアンドリュー・ランサンガンのオルガンを前面に押し出したゴシックで歪な箱庭を展開。再生した瞬間から大きな衝撃を受けたし、ほとんどの曲がスローペースになっていて、ソウルフルなロウのボーカルとは対照的にブライアン・ケースのボーカルはシャウトを抑えて陰鬱に言葉を連ねていく、二人のボーカルが入れ替わりユニゾンしていく様が素晴らしい。一音一音を大切に聴かせるそぎ落とされてサウンドスケープがとにかく美しく、とくに臨場感のある生々しいドラムの録り音はスケールの大きな曲の世界観をあえて小さい密室に閉じ込めるような雰囲気がある。またこれ以降長く交流が続くジョン・コングルトンが初めてプロデュースを担当したアルバムでもあり、彼の功績も大きかったのではないかと思われる。コングルトンはアルビニのスタジオで働いてた経歴があり、尚且つSouthern RecordsやKill Rock Starsからアルバムを出していたThe Paper Chaseのメンバー。このバンド自体の音楽性も非常に同時代性が強い。今作全く予想してなかった新たな地平を見せられたことで、SlintやDon Caballeroといったわかりやすい記号とリンクさせて聴いていた自分の浅はかさを思い知ったし、最初から別物だったのではとすら思えてしまう。オルガンのパートがフィーチャーされたことから耽美な空気感が増していて4AD時代のBlonde Redheadが好きな人にもフィットするかと。

2004年にリリースされた3rd。90 Day Menとしては最後のアルバム。2ndの路線の更に奥へと推し進め、単音メインの乾いたギター音へと変貌しちょっとKarateも思い出す。循環するオルガンのリフレインと隙間を埋め合うよう纏わりつくリズム隊のループは初期とは全く違った方向性でマスっぽさが増していて、アコースティックを取り入れた曲もありこの反復メインの生音ポストロック~ほんのりクラシカルな雰囲気はDirty ThreeとかRachel'sもちょっとだけチラつくけど、その辺とは一線を画した歪な聞き味を生むロバート・ロウのボーカリゼーションがすごすぎる。M1から色鮮やかで自由な歌声はより一層ソウルフルになっているし、酩酊するようなふわふわとしたサイケデリアは後のDisappersやFACSでは見ることができないコラボレート。むしろDisappers以降のポストパンク~インダストリアル要素を見るとブライアン・ケースのSwans的な趣向も見えてくる。ロバート・ロウはこの後LichensやRobert Aiki Aubrey Lowe名義でアルバムを発表、電子音楽の色を強くし独自のキャリアを展開していく。

90 Day Menのフロントマンであったブライアン・ケース率いるDisappearsの1st。この頃は割と直線的な8ビートのガレージポップで、歪みの強いぼやけたノイズやリバーブがかかったボーカルが印象的で比較的00s~10年代初期のブルックリン系のインディーロックやCaptured Tracksといったドリームポップと並べて聞くことも可能。というか海外メディアでシューゲイザーとして語られていることもある。ブライアン・ケースが90 Day Men終了~Disappears始動までに在籍していたThe Ponysも少し想起する。Ponysはガレージ色の強いインディーロックで、地味にこちらはアルビニ録音で作品を残していたりする(90 Day Menはグレッグ・ノーマン及びジョン・コングルトンというアルビニの弟子とも呼べるプロデューサーと組んでいたが、アルビニ録音は一枚も残していない)。
Disappears - Pre Language(2012)

Sonic Youthのスティーヴ・シェリーが参加した2012年リリースの2nd。前作同様ポストロック名門Krankyからのリリース。音楽性面で大きな評価を得たのは次作以降のEra/Irrealだけど、スティーヴ・シェリーの存在からか今作も比較的バンドを語る際に挙げられがちなアルバム。まだ前作の流れを汲んだガレージポップではあるんだけど、ガレージっぽさは減って今作の方が隙間があって音の抜け感が強い。M1のReplicateで聞けるシンプルなハンマービートは、次作以降のクラウトロック路線も垣間見えスカスカであることがよりマッチしている。M2のPre Language、M5のAll Gone WhiteはDisappearsにしてはインディーロックとしても聴きやすい曲だと思う。
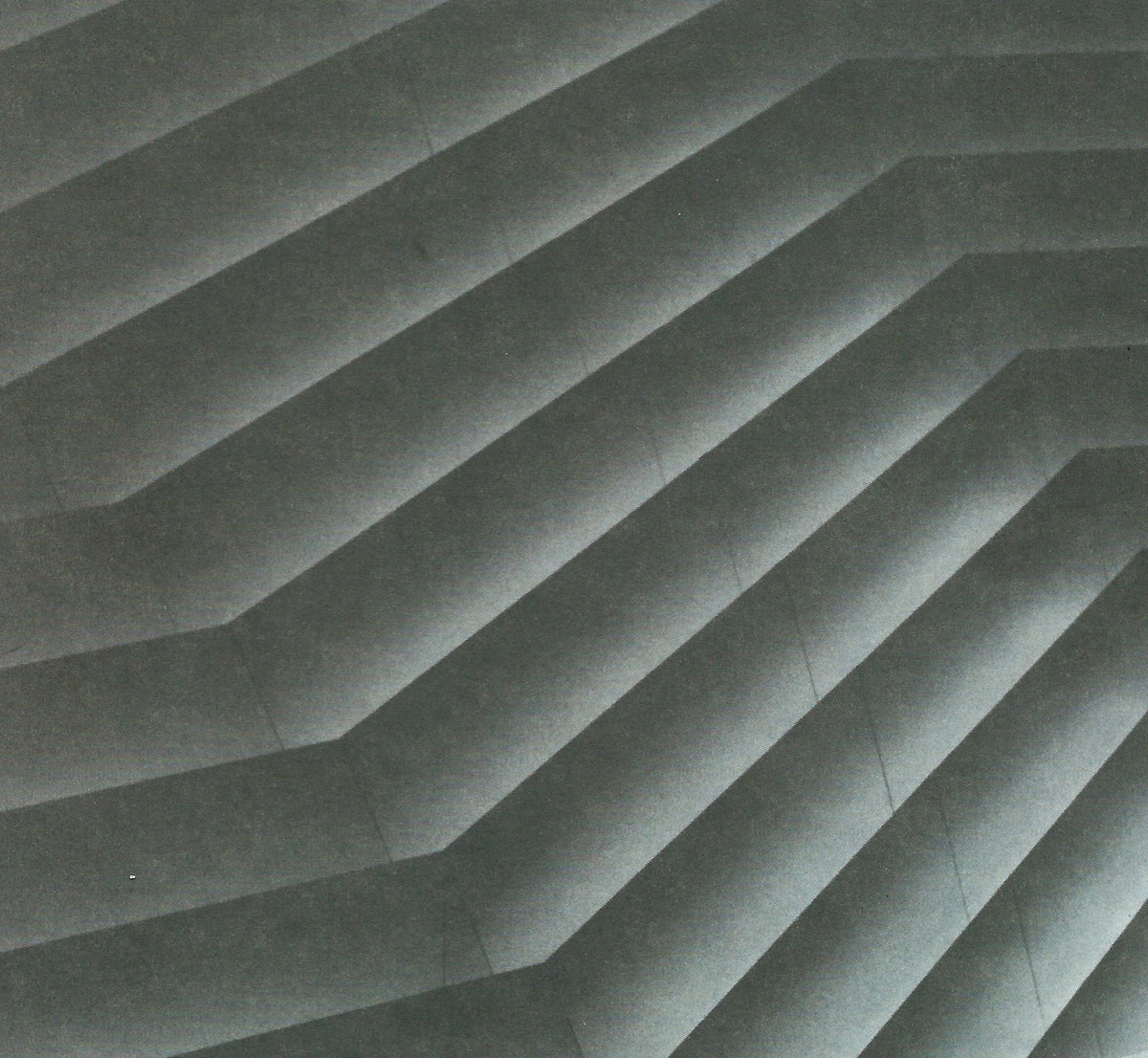
2013年リリースの3rd。スティーヴ・シェリーは脱退し、代わりにSpeaking Canaries/Hurlといったピッツバーグシーンで活躍したノア・レジャーがドラマーとして加入。後のFACSへの萌芽ではあるが今作にしかない独自のサイケデリックな実験精神が爆発しまくっていて痛快。M2のPowerで聞けるドロドロとした心地悪い音色を聞かせるギターサウンドと、前作と比べるとメロディーが抑制された陰鬱なボーカル、消え入るような不穏なノイズと前作で垣間見せたクラウトロック的な反復、あえて淡々と刻むことで浮き上がってくる密室的な空間の聴かせ方は90 Day Menの2nd以降プロデュースを担当しているジョン・コングルトンがここにきてまた冴えまくっていてヤバイ。M3のUltraはNeu!みたいな無機質の反復とJoy Division直系のポストパンク路線が境界なく溶け合い、呪術的でトライバルな要素も合流。M6のElite Typicalは曲自体が今作でコントラストとなるアグレッシブなビートがかっこいい。ズブズブと少しずつ足元から沼に沈んでく感じはメロディだけでもまだ聞けた前作とは対照的、それでいて90 Day Menの顛末とは完全にイフルートの独自のワールドを展開した名作。Preocupessions(ex.Viet Cong)とかとも近い。
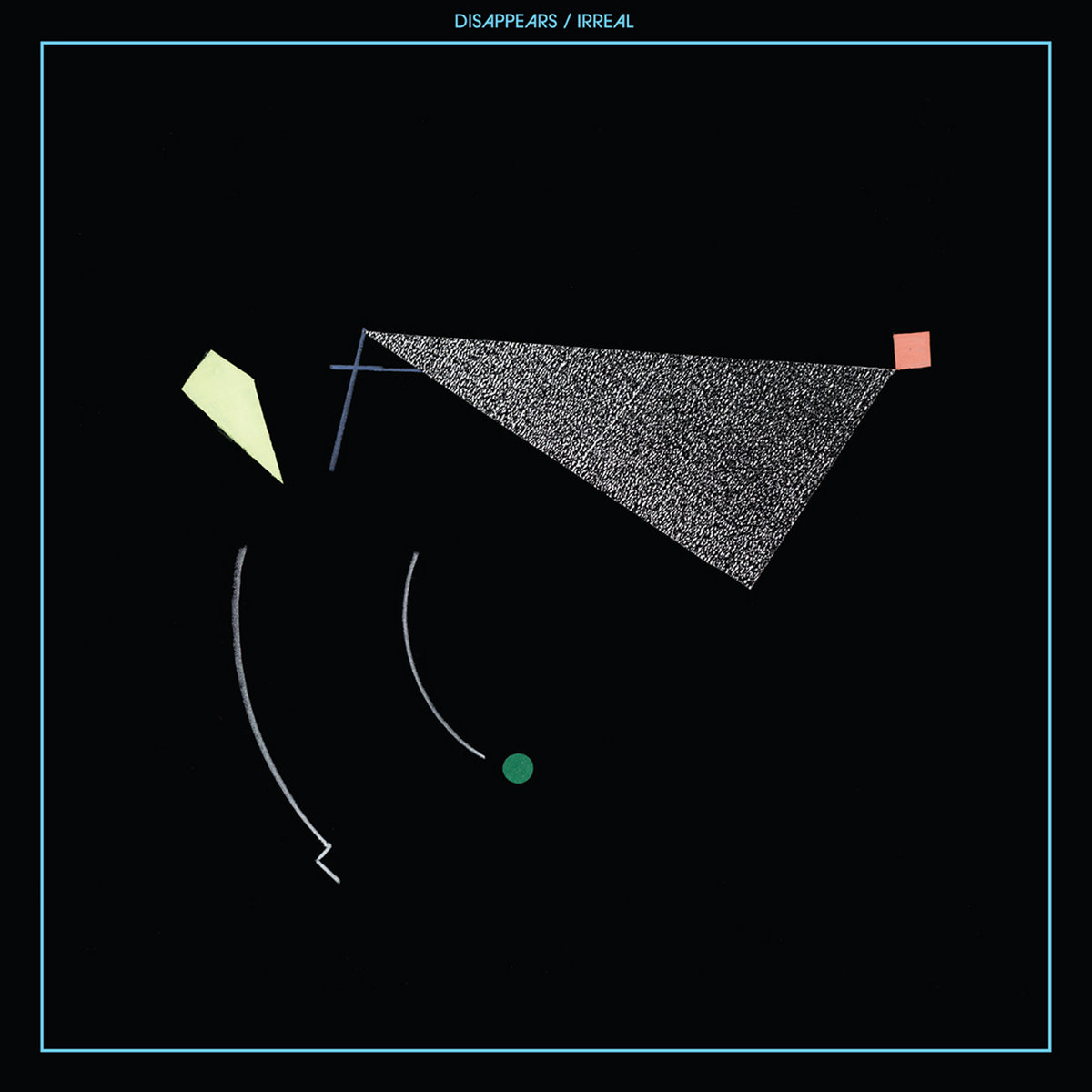
Eraに引き続きリリースされた今作はEraの暗黒クラウト/ポストパンク的な路線を更に推し進め、いくとこまでいっちゃったロックバンドという枠組みに擬態した人力インダストリアル。各種メディアからも高評価を受けた作品で、今作もプロデューサーはジョン・コングルトン。彼は同時期にXiu Xiuのプロデュースも担当しているけど今作はとくに強いリンクを感じる。メロディが希薄であること、ゴシックでダークな音空間から前作の延長線とはいったけど、Eraにおけるズブズブと下へと潜っていくようなドラムの音とは全く真逆、M1のIntegrationからむしろ跳ね返ってくる硬質で跳ねた音になっていて、クラウトロック直系の直線的だったEraとは異なるビート感がより際立っている。ビートが断続的になったことでスネアの焦点が合う感じは以前よりカッチリした印象、それでいてミニマルで、相変わらず幽霊みたいなボーカルも相まって呪術的な要素は増した気もしてIrreal=非現実というタイトル通り全く知らない世界を目の前にしてるようなアルバム。静寂のイントロから潰れた低音の威圧感が半端ないM4のIrreal、スカスカのビートにドロドロに溶けたギターリフが表出するM5のOUD辺りもめちゃくちゃかっこいい。

FACSはDisappearsからメンバーが一人離脱し、ブライアン・ケースがベースボーカルに転向する形で新体制の3ピースバンドへ。メンバー的にも今作はまだDisappearsの続編感が強いけど、M1のSkylarkingから深淵の底に取り残されて闇に埋没してくようなNick Cave × P.i.L.のFlowers of Romanceなトライバルなビートの映えるゴシックなポストパンク。Siouxsie And The Bansheesもちょっと入ってる。リズムに比重が乗ったというか、全体的にズッシリ重心が乗っててM3のHouses Breathingも8分超あるM1と同路線。Eraの延長線上ではあるんだけど、FACSってDisappearsと比べてかなり「バンドっぽい」音がするのが良い(3ピースというのもあるかと思う)。Disappearsがロックバンドの皮を被って電子音楽を演奏するバンドだとしたら、FACS以降はそれを血肉化した上でストレートにギター/ドラム/ベースがぶつかり合ってスタジオで鳴ってる景色が見えてくる気がする。
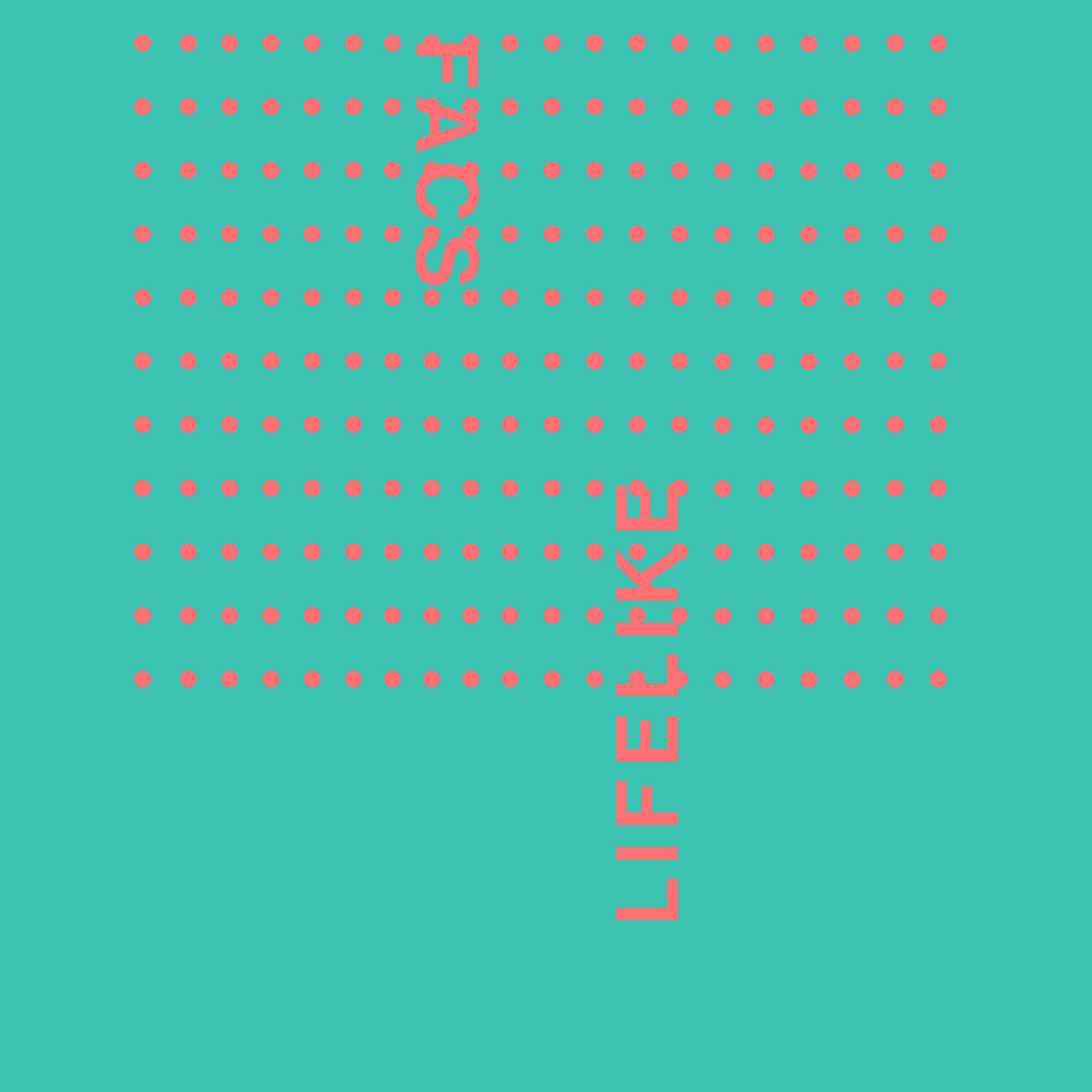
翌年にリリースされたFACSの2nd、メンバーが入れ替わりブライアン・ケースは再びギターボーカルに、プロデューサーとして旧知の中であるジョン・コングルトンも再び合流。かなりミニマルになっていて跳ね返って溶けてくようなギターのテクスチャはとてもポストパンクっぽく、乱反射するギターの粒が空間そこら中に散っていく感じはポストロックにも通じる。M3のXUXAあたりから今後続くちょっとThe Cureっぽい感じが出てきた気がする。

2020年リリースの3rdでM1のBoyから最高。ヘッドホンで聞くと脳内バグったかと思うサウンドスケープに頭をシェイクされる。物理的に触れるんじゃないかと錯覚するくらい立体的に各パートが入れ代わり、地の奥から湧いてくる低音に仰天。これはもう録音作品じゃないとなし得ないサイケデリックな音空間、ここから現在の最新作まで続く新たな路線を開花させた覚醒の一枚。ドローンっぽい音色や全体を覆いつくすぼやけた音空間も際立っていてSonic Youthとのリンクも強い。次作以降見せる歪みまくったベースは本当に低音がえげつなく、グイグイとバンドを牽引していてちょっとダビーになったThe Cureみたいな雰囲気もある。この辺の熱さと幻想的なドロドロっとした触感がより過剰に、そしてシャープになっていく終着点として次作の大傑作4thがある。

Era~Irreal期のDisappearsを降ろしてFACSの形態で昇華したノイズロック路線の決定版とも言えそうな21年リリースの4th。ここまで結成から毎年リリースしてきたFACSだけど、ここで一旦の到達点として聴けそうな集大成にして名盤。1stにあったニック・ケイヴやバンシーズみたいな路線が好きな人にも絶対に間違いないでしょう。自分はリアルタイムで初めて聞いたFACSでもあり、90 Day Men終盤の耽美でサイケデリックだった作品群とは完全に切り離された、全く違うハードSFな暗黒世界にかなり衝撃を受けてそっから貪るようにアルバムを辿っていくことに。M1のXOUTから一生反復するんじゃないかと思うくらい中毒性のある、地をのたうち回る爆低音のベースのループ、纏わりつくように変化し続けるドラム、音色ではなくプレイそのものが歪んでると形容したいフリーキーなギターワーク、あと呪術的で時折ヒステリックに言葉を連ね続けるおどろおどろしいブライアン・ケースのボーカリゼーション・・・本当に凄まじい。音に体を委ねトリップしていると徐々に演奏がアッパーになっていきいつの間にかバーストへ。ロック的カタルシスもしっかりあり、というかむしろFACSの中ではかなり熱い着地点に向かっていくため初期90 Day Menと比較できるかもしれない。ドリーミーな雰囲気でめっちゃポップなM2のStrawberry CoughもFACS随一に聞きやすい新たな代表曲。キラキラとうねりを上げるギターサウンドが美しい。フェードインでイントロから没入感のあるM3のAlone Withoutはねばついた激重グルーヴで9分超あるバンドの皮を被ったドローンナンバー。1stにもあった路線で個人的に今作で一番好き。Unwoundがもし解散しなかったらこうなってたかもなーという妄想をしてしまいますね。
FACS - Still Life In Decay(2023)
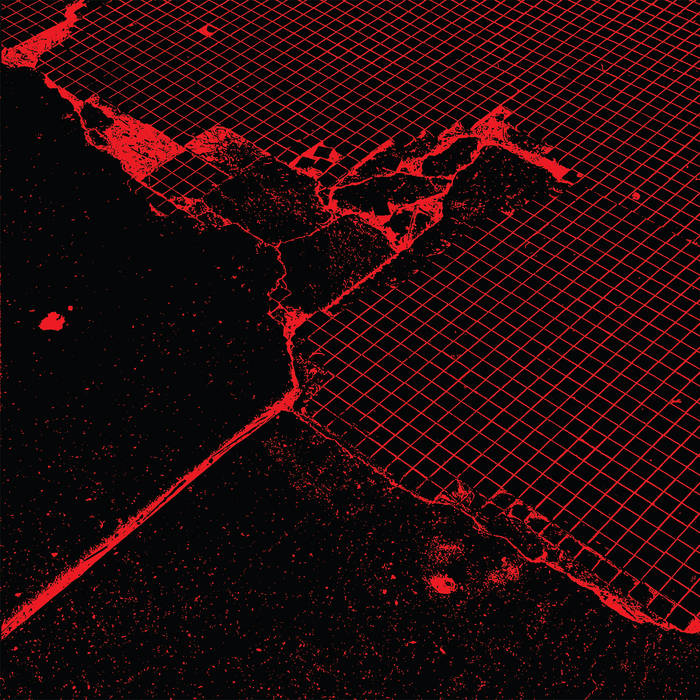
ブラックホールに放り込まれたみたいなM1のConstellationから死ぬほどかっこいい。今作もリリース当初聴いてかなり衝撃を受けた作品。ポストロック黎明期に実験を繰り返しシーンを支え、一回リセットしてクラウトロックもインダストリアルも自己解釈で再定義した上でもう一度ポストパンク/ポストハードコアに回帰したのがおそらくこの頃のFACSである。ある意味で円熟を見せたとも言えるアルバムではあるが、20年以上の月日とキャリアが伴ったことで、ポストパンクとかポストハードコアとは言いつつも全然知らない見たことない姿で顕現している。M2のWhen You Sayは機械的なドラムとそれを下からグイっと持ち上げるうねる超低音のベースラインは人力マシンビート的、2:50〜の地盤が揺れるんじゃかいかと思うくらい強烈な歪みが曲全体を揺らす部分は笑顔が止まらない。不穏で冷たいリズム隊の反復からストレートに熱いギターソロ、そしてノイズパートが用意されているし、前作のStrawberry Coughもそうだけどここにきてストレートなアンセムが真っ向から来ることが本当に熱い。純粋にバンドの間口を広げてくれると思う。前作で見せたサイケデリックな音の広がりを一回バンドサウンドとして凝縮して吸収した雰囲気があるし、これがよりラフな最新作へと通じていく。
ちょうど出た頃にModel/ActrizやViagra Boysといった新気鋭の尖ったポストパンクがリリースを連ねていて同時代のFontaines D.C.の2nd~3rdあたりとも呼応してるなと思ったし、とくにGilla Bandの名ライブ作品Live at Vicar Streetが好きな人には是非FACSを聞いてほしい。それこそ実験作を積み上げてシーン自体が大きく変貌していったサウスロンドンやダブリンのシーンと並べて聞ける作品だと思う。

今年リリースされたばかりの話題作。4thでEra以降のサイケデリックな音空間は一度区切りを見せ、5thからはポストハードコア通過後のゴリゴリのポストパンクへと収束→それをアルビニ録音により推し進めたキャリア内屈指に肉体的なアルバムが今作。エレクトリカル・オーディオなのでもう当たり前っちゃ当たり前だけどドラムの音があまりにも良く生々しい臨場感がしっかり箱庭に閉じ込められている。もう芸術的とも言える隙間を埋めつくすブライアン・ケースの幻想的なギターワークは鋼のようなリズム隊を逆に浮き上がらせ、激しいエネルギーが内へと向かってくような強靭なアルバムになってると思う。あと今までで一番じゃないかというくらい曲がポップなのも印象的。とくにM3のWish DefenseはOmniも思い出す風通しのいいポストパンク。後半はしっかりドロドロとしたFACSワールドへ。M2のOrdinary VoicesはTha CuraのFaith期~Siouxsie And The BansheesといったゴスからUnwoundまで連想。NUMBER GIRL好きな人とかにも聴いてほしい。
また今作はアルビニが最後に手掛けた作品としても知られていて、亡くなる数時間前まで普通に会話してたとブライアン・ケースが語る海外メディアのインタビューは胸が苦しくなる。レコーディングは終えてあとはミキシングという段階だったらしく、エレクトリカル・オーディのスタッフであり、共通の友人でもあるサンフォード・パーカーが手を貸してくれたり、旧知の中であるジョン・コングルトンが状況を知って連絡してくれて、今作を一緒にミックスしてくれたというのもグッとくる。とくにジョン・コングルトンは今ではグラミー賞のアーティストも手掛けた大御所になってしまったけど、元々シカゴにいた頃はアルビニのスタジオで学んだことをインタビューなどで多数語っているのも熱い。アルバムについても多数語られているので以下リンクを貼っておきます。
またFACSは昨今話題になることが多いシカゴのインディーシーンの中でも非常に重要なバンドで、FrikoやHorsegirlと並んで同シーンで活動しているLifeguardというバンドのベース/ボーカルのアッシャー・ケースはブライアン・ケースの息子だったりする。Lifeguardはちょっと前にインディー名門Matadorと契約してブライアン・ケース自体が息子のバンドに触れてる記事も同メディアから出ていて、オープニング・アクトをやりたいと言ってるのもおもろい。シカゴはそれこそTouch and GoやDrag Cityといったあの頃を象徴するレーベルの拠点でもあり、FACSのようなレジェンドがしっかり現行シーンとハブがあるのはシンプルに熱い。あとLifeguardはHorsegirlのメンバーの兄弟も参加していてこの辺の地域のコミュニティも盛んなようだし、同シーンのFinomはメンバーにWilcoのジェフ・トゥイーディーの息子がいたりする(彼らもシカゴ在住)。Lifeguardもエレクトリカル・オーディオで録音していて親子揃ってアルビニのスタジオで録ってるのもすごい。この辺のコミュニティはHallogalloという名前があるらしく昨年のミューマガで詳しい特集が組まれてました(ミュージックマガジン2024年10月号)。
ブライアン・ケースが息子について語ってるインタビューはこちら。MetzやPreoccupationsとツアーをしたときの話や最新作に至るまでのFACSのメンバーの変遷にも触れられている。
Disappears - Disappears + Steve Shelley + White/Light(2020)

番外的に最後にちょっとだけ。DisappearsにSonic Youthのスティーヴ・シェリーが加入するちょっと前、Disappearsの面々とスティーヴ・シェリーとWhite/Lightというバンドのメンバーによるセッションを元に作られた未発表音源集が2020年にリリース。めちゃくちゃ良い。Fishtank的な企画物かと思う。かなりスペーシーでそれこそクラウトロック的な方面に舵を切る直前、実際その要素を醸造したかのような古のSFサントラみたいで素晴らしい。個人的に後期OGRE YOU ASSHOLEを思い出した。
Disappears - Low: Live In Chicago(2015)

こちらは2015年にDisappearsがデヴィッド・ボウイのLowをカバーしたライブアルバム。ベルリン期を象徴するみたいな作品でDisappears後期~FACSのルーツとしてまんま答え合わせみたいで楽しい。Lowはボウイのキャリアの中では個人的にStation to Stationと並んで最も好きなアルバムなのでとても嬉しいし、What in The Worldが早急なツインギターのアンサンブルで風通しがよくなっててぶち上がってしまう。B面のインストパートもハマりすぎててすごい。圧巻。
以上です。FACS来日公演の初日(5/1)行った後に書いてますがまだ公演いくつか残ってるのでぜひとも。ライブレポも後に書きたい。
あと作中ちょっと触れてますが90 Day Men後期は今聞いてもやっぱり異質、この音楽性の秘密はマルチプレイヤー及びベース及び終盤2作ではボーカルを担当したロバート・ロウのおかげだと思っていて、彼のキャリアについてはこちらの記事で大きく触れられています。